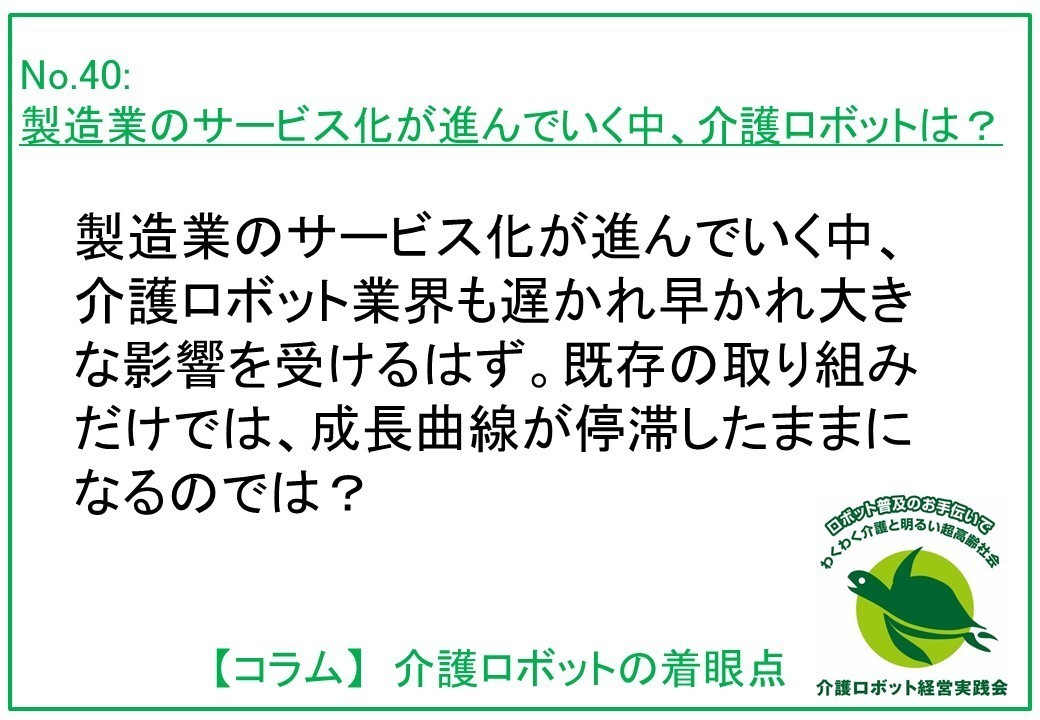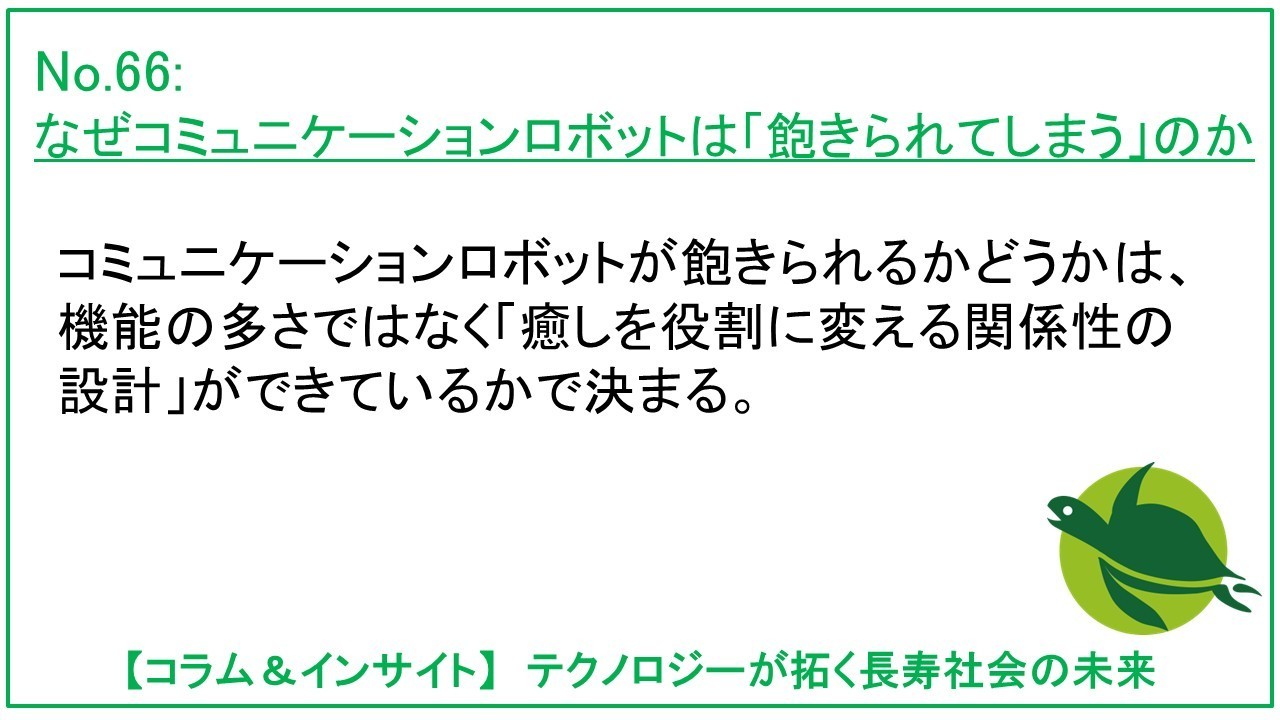2019年 4月18日(木)
【キーワード】
- 製造業のサービス化
- 売り切りモデル
- 従量課金
政府の日本再興戦略に盛り込まれた「ロボット介護機器開発5ヵ年計画」では、「2020年までに市場規模500億円!」というターゲット(数値目標)が掲げられました。
あれから5年以上が経過し、残りあと1年ほどですが、果たして目標の達成は可能でしょうか? おそらく、今の「成り行きのシナリオ」ではとても無理でしょう。
ところで、介護ロボットの市場は、今後、どのように形成されていくのでしょうか? 介護保険の給付「対象」および「対象外」と、大きく2つの市場が形成されるでしょうが、前々から私は3つにセグメント化が進むと予想していました。
1つ目は、介護保険の給付対象となり福祉用具の延長上に形成される市場です。2つ目は、コモディティ化した家電のような市場です。ローエンドの製品が対象となります。3つ目は、必ずしも保険に依存しない高価格・高付加価値のハイエンドの製品から成る市場です。
「大きく3つの市場にセグメント化される」と予想していますが、それぞれが同じタイミングで成長するとは全く思っていません。それは他の市場を見ても明らかです。
おそらく、最初に成長が見込まれるのは、2つ目のコモディティ化した家電のような市場だと思っています。「家電のような」と書いたのは、わざわざ保険制度に頼るまでもない価格帯という理由からです。
例えば、シャープのロボホンのようなロボットは、AIスピーカーなどと同じように一般の消費者の間に広がっています。また、見守り機器についても、安価なものであればこのセグメントに該当します。安価なので、なにも保険制度に依存しなくても購入してもらえるのです。
ただし、このセグメントに関し、懸念していることがあります。それは、諸刃の剣である補助金制度の影響をマイナスに受けるかもしれないことです。安価で良い製品であっても、自治体などが毎年発表する補助ロボットのリストに載らないと、買い手である介護施設の「買い物リスト」から外されてしまうからです。
「No.30 成功への第一歩はメニューに載ること?」のコラムにも書きましたが、私たちがスーパーで買い物をする際、「今日は○○を買うんだ!」とあらかじめ意識していないと、お得感から必ずしも必要ない「半額のシール」が貼られた食品の方についつい目が奪われてしまいます。
介護ロボットの購入でも、これと同じことが起こります。つまり、「せっかくなら補助金対象のリストの中から選ぼう!」という意識が働くことです。そうやって買い物リストの候補から外されてしまうと、安価で良い製品であっても購入検討の対象にならないのです。
また、1つ目の介護保険の給付対象となり福祉用具の延長線上に形成される市場については、「今のままだと停滞するのでは?」と心配しています。
というか、「福祉用具の延長上のごとく」と書きましたが、「福祉用具と同じような制度が、将来の介護ロボットに果たして適用できるのだろうか?」と心配しています。
なぜなら、既存の福祉用具の制度は、機種・製品毎の「売り切り」のサービス(実際にはレンタル)を前提にした制度だからです。しかも、スタンドアローンと同じ使われ方が前提になっています。
ローテクの製品には都合が良いかもしれません。しかし、今、製造業のサービス化が進んでいます。従来の製品の売り切りモデルが大きく変わりつつあります。
モノは時間の経過と共にコモディティ化するので、モノ以外の付加価値を提供し、課金する動きが広がっています。IoTの普及により、例えば「モノはタダで提供しますが、使った分だけ料金をいただきます!」という従量課金の制度が浸透しつつあります。
また、IoTの普及は、製品毎のスタンドアローンのような使われ方を大きく変えます。モノの機能面の価値よりも、例えばビックデータを活用し、付加価値を付けたサービスなどが重要になってきます。
製品単体でなく、サービスと組み合わさった顧客への価値提供が一般化します。
だから、福祉用具の延長線上に制度をつくっても、時代の変化に追いつかないまま、10年も経たずに廃れてしまいかねません。
一部の専門家の口から「介護ロボットは、福祉用具が高機能化しただけ」などという発言を耳にしたことがありますが、目の前に広がっている世界は、単に福祉用具の高度化や高価格化とはかなり景色が異なるはずです。
今は将来の制度設計が不透明なまま、国や自治体から単年度毎に実施される補助金制度を当て込み、市場が成立しているという感じです。果たして今の状態がいつまで続くのでしょうか?
3つ目の高価格・高付加価値のハイエンドな製品については、市場の成長はまだちょっと先のことになると予想しています。
おそらく、このような製品について関係者に意見を聞きに行けば、「そんな高い製品は、この業界では売れないよ!」「どこも保険給付を当て込んでいるんだよ!」などと言われるだけでしょう。
だから、そのような発想しかできない人ではなく、「どうしたら1,000円のモノを5万円でも売れるできるか?」などと考える人に当たるべきでしょう。デビアス社が、本来の価値よりも遥かに高い価格でダイヤモンドを普及させたの同じようなスキルが必要だと考えています。
また、介護施設の中には「新しい技術が出てきたら、とにかく何でも試してみたい!」という人もいます。そういう職員が在籍している一部の施設が「無料で使わせてくれるなら、ウチが使って、コメントをフィードバックしてあげる!」などと言ってくれるはずです。
しかし、「どうやって集客し、マネタイズするのか?」という非常にチャレンジングな課題に直面します。
ニーズやウォンツはあるのに保険適用の対象外となっている美容整形や民間療法のサービスのように、「高額でもOK!」「自腹を切ってもいいから、ぜひ、欲しい!」と需要を喚起させる必要があります。当然ながら、それには特別なマーケティング活動が必要となり、それなりのコストが掛かります。
巧みなマーケティングを展開している、美容整形業界の高須さん(高須クリニック)さんや相川さん(湘南美容クリニック)などは明らかに異端児です。だから、上手くいくのでしょうが、杓子定規な考え方をする人、常識だけで判断する人の集団ではかなり苦戦するはずです。
美容整形の場合は、新規顧客の獲得にコストが掛かっても、鼻から始まり、次に目を、それからお尻・・・と、次から次に異なるパーツの手術を施すことで、顧客1人当たりの売上を可能な限り大きくします。
鍼のような民間療法についても、繰り返し来院してもらうリピートによって顧客1人当たりの売上を最大化させています。
だから、「1台売ったら、それっきり!」という、既存の製品の売り切りモデルでこのセグメントを切り開こうとするだけではなく、「どうやって集客し、どのタイミングで損益分岐となり、どうやって収益を最大化するのか?」というシナリオをあらかじめ設計した上で、それを検証しながら改善していく取り組みが必要です。
結局のところ、製造業のサービス化が進んでいく中、介護ロボット業界も遅かれ早かれ大きな影響を受けるはずです。
自治体などに働きかけてロボット導入に前向きな施設の職員を集めたセミナーを開催してもらい、そこで展示(プロモーション)の場を得る、という既存の取り組みだけでは、成長曲線が停滞したままになるのではないでしょうか?
セキグチについて

「いきいき長寿社会推進者セキグチ」の関口です。
テクノロジーを通じて、高齢者がより豊かに社会とつながる未来を目指し、介護ロボット分野から一歩広げた活動に取り組んでいます。私の経歴やこれまでの取り組みについては、プロフィールページで詳しく紹介しています。
また、活動の背景や大切にしている考え方は、ビジョン・メッセージページにまとめています。ぜひあわせてご覧ください。
最新コラム&インサイト
過去のコラムでもお伝えした通り、PAROやLOVOT、NICOBOといったコミュニケーションロボットは、「癒し」「話し相手」「孤独の解消」といった文脈で広く語られるようになりました。実際、それらは確かに重要な価値です。
しかし、現場で導入が進むにつれて、もう一つの大きな課題が浮かび上がってきています。それは、「最初は盛り上がるが、時間が経つと飽きられてしまう」という問題です。…
テクノロジーが拓く長寿社会の未来
テクノロジーと社会参加の両面から、長寿社会をより豊かにするための視点をわかりやすくお届けしています。
最新のお知らせ
2025年11月18日(火)
「介護ロボット経営実践会」に代わり、新ブランド「いきいき長寿社会推進者 セキグチ」として新サイトを公開しました。