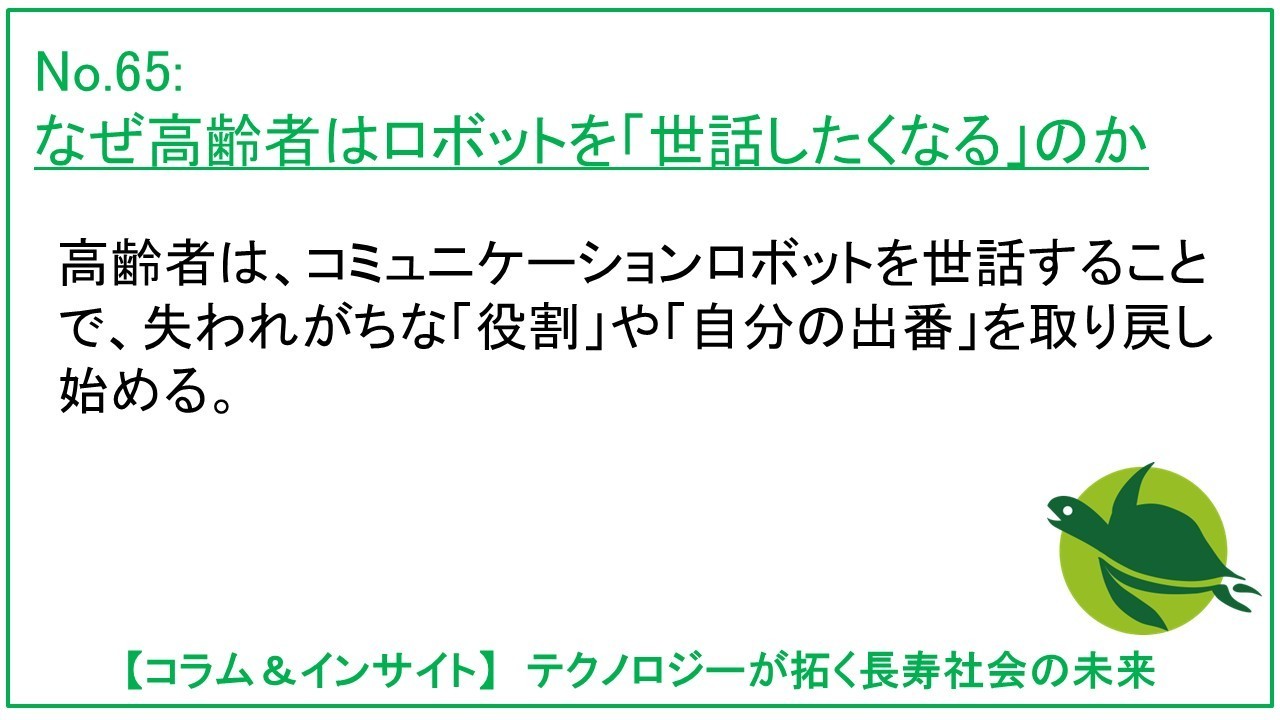プロフィール
幸齢社会を拓くために、人と技術のあいだを“翻訳者”としてつないでいます。
自己紹介

高齢期を、支えられる時間としてではなく、役割や出番がもう一度立ち上がる時間として捉え直すこと。
それが、私の活動の出発点です。
2010年から介護分野でロボットやICTの普及・促進活動に関わる中でテクノロジーは「導入すれば解決するもの」ではなく、人や暮らしとの関わり方によって意味が変わるものだと実感してきました。
現在は、特定の立場や役割にとどまるのではなく、テクノロジーと人、暮らしと社会の関係性を見つめ直しながら、年齢を重ねても誰もが役割を持ち続けられる「幸齢社会」のあり方を考え、発信しています。
こうした視点の原点には、学生時代の体験があります。
経歴ストーリー
アメリカで見た「年齢に縛られない暮らし」への驚き
この道を歩む最初のきっかけとなったのは、高校時代に留学したアメリカでの経験でした。そこで目にしたのは、年齢を重ねても自分らしく、いきいきと暮らす高齢者たちの姿です。
例えば、80代の赤いシャツを着たオシャレなおばあさんが、大きなピンクのキャデラックを危なっかしそうに運転しながら、うっかり逆走してしまう――そんな“元気すぎる”姿さえも印象的でした。
1980年代のことでしたが、当時から私は、日本の高齢者像とは大きく違う「年齢に縛られない暮らし方」を肌で感じていました。

再びアメリカへ:MBAとリタイアメントコミュニティの衝撃
アメリカの大卒後は日本でオリンパスに勤務し、その後、経営大学院でMBAを取得するために再びアメリカへ渡りました。
大学院の近くにはリタイアメントコミュニティ(高齢者のための街)が広がり、そこで私はさらに鮮烈な光景を目にします。
昼間はゴルフやテニスを楽しみ、夜になると、夫婦や友人同士の高齢者がカジノでスロットマシンを回しながら、笑い合い、時間を忘れて楽しむ姿――。
そこでは、「高齢者が人生を楽しみ、活躍の中心にいる生活」が当たり前でした。
こうしたアメリカでの体験が、私の中に「日本にも、高齢者が主役として活躍できる社会を!」というビジョンを、静かに、しかし確かな形で根づかせていきました。

日本での実践:健康食品から介護ロボットへ
アメリカで見た「年齢に縛られない暮らし」が心に残っていた私は、日本でも高齢者がもっといきいきと過ごせる社会をつくりたいと思うようになりました。
その最初の実践が、中小企業の新規事業として取り組んだ健康食品の販売でした。広告づくりやニュースレターでは、“アクティブ”“いつまでも生き生き”といった表現を自然と使い、「年齢を重ねても自分らしく生きる」というテーマを常に掲げていました。
しかし、活動を続ける中で「商品を届けるだけでは、本当の意味で高齢者の生活を変えられない」という感覚が強まっていきました。
そう感じていた矢先、2010年に神奈川県事業として始まった介護ロボット普及推進プロジェクトに、実行チームを取りまとめる役割として参画する機会を得ました。
そこでは、現場・行政・企業をつなぐ“橋渡し役”として、数多くの導入支援や調整業務に携わりました。
介護現場の目線に合わせて、行政や企業とのあいだに生じる認識のズレを埋めながら進めていく中で、メディア取材や議員視察への対応も増え、活動の幅が大きく広がっていきました。
こうした経験を通じて私は、「人 × 技術 × 現場」をつなぎ、前向きな流れを生むことこそ、自分が一番価値を発揮できる役割だと強く実感するようになりました。

高齢者が主役となる「幸齢社会」を目指して
介護ロボットの普及に関わる中で、技術が人の負担を減らすだけでなく、人の力を引き出し、現場や組織の空気を少しずつ変えていく場面に、何度も出会ってきました。
そうした経験を重ねる中で、高齢者は「支えられる側」にとどまる存在ではなく、関わり方次第で、地域や場を動かす側にもなり得るのではないか。
そんな考えを持つようになりました。
日本では、「高齢」「介護」「老後」といった言葉に、どこか後ろ向きな印象が伴いがちです。
しかし私は、その前提自体を問い直す必要があると感じています。
介護ロボットの普及に携わる中でも、目的は単なる人手不足の解消や業務の効率化ではなく、介護の現場を「人が関わり続け、活躍し続けられる場」としてどう捉え直せるか、という点にありました。
年齢に関係なく、誰もが役割を持ち、自分なりの出番を見つけていける社会。
それが、私が考える「幸齢社会」です。
この考え方は、これまでの仕事を通じて形づくられ、今も活動の軸として大切にしている視点です。
運営母体と活動ブランド
運営母体
株式会社とげぬき(代表取締役)
活動ブランド
1)いきいき長寿社会推進者 セキグチ
超高齢社会において、テクノロジーと社会参加の関係を問い直し、高齢期の「役割」や関わり方をひらく活動を行っています。
(※旧「介護ロボット経営実践会」。介護現場での経験を起点に、活動の焦点を「役割」や「関係性」へと広げています。)
2)戦略プロセス経営実践会
中小企業の事業戦略づくりや顧客獲得・ブランド構築を支援しています。
(※高齢社会の活動とは別ブランドとして運営しています。)
領域は異なりますが、両者に共通する軸があります。
それは、「人と組織が、自分たちの強みで前に進むプロセス」をつくること。
私は、現場・組織・地域に寄り添いながら、持続的に成果が生まれる仕組みづくりを大切にしています。
講演・取材のご依頼はこちら

講演・研修、企業・自治体での対話セッション、
高齢社会・エイジテックに関するご相談など、
ご関心がありましたら、お気軽にお問い合わせください。
内容のご相談段階でも歓迎します。
セキグチについて

「いきいき長寿社会推進者セキグチ」の関口です。
テクノロジーを通じて、高齢者がより豊かに社会とつながる未来を目指し、介護ロボット分野から一歩広げた活動に取り組んでいます。私の経歴やこれまでの取り組みについては、プロフィールページで詳しく紹介しています。
また、活動の背景や大切にしている考え方は、ビジョン・メッセージページにまとめています。ぜひあわせてご覧ください。
最新コラム&インサイト
PAROやLOVOT、NICOBOといったコミュニケーションロボットについて語られるとき、「癒し」「話し相手」「孤独の解消」といった言葉がよく使われます。
確かにそれらは、ロボットがもたらす大切な価値の一部です。…
テクノロジーが拓く長寿社会の未来
テクノロジーと社会参加の両面から、長寿社会をより豊かにするための視点をわかりやすくお届けしています。
最新のお知らせ
2025年11月18日(火)
「介護ロボット経営実践会」に代わり、新ブランド「いきいき長寿社会推進者 セキグチ」として新サイトを公開しました。