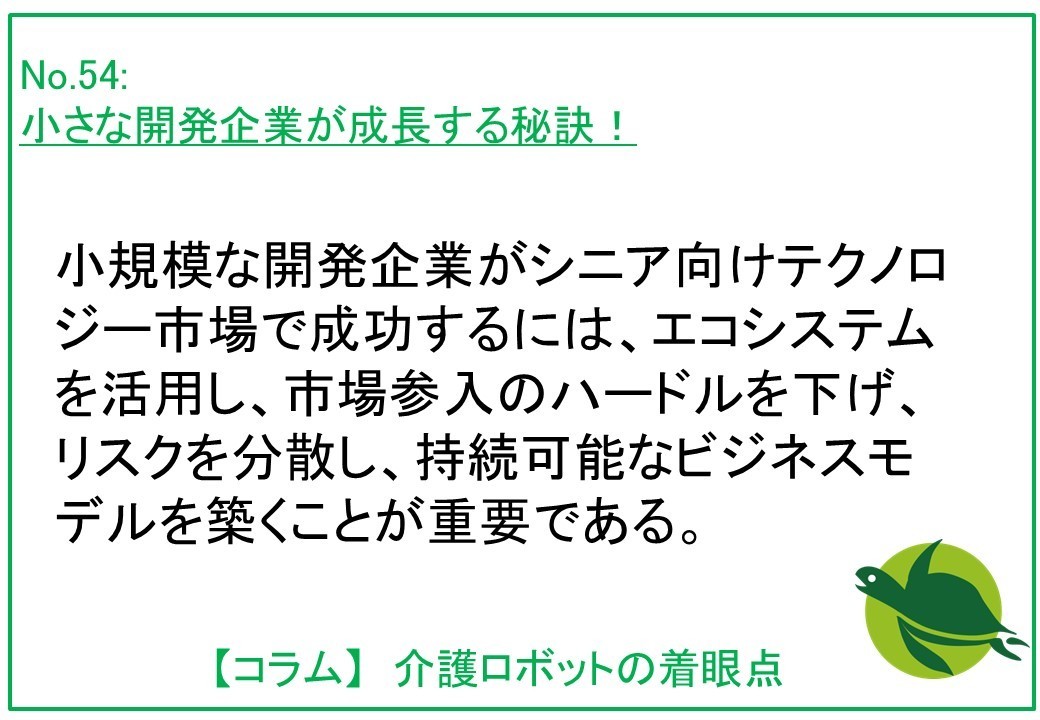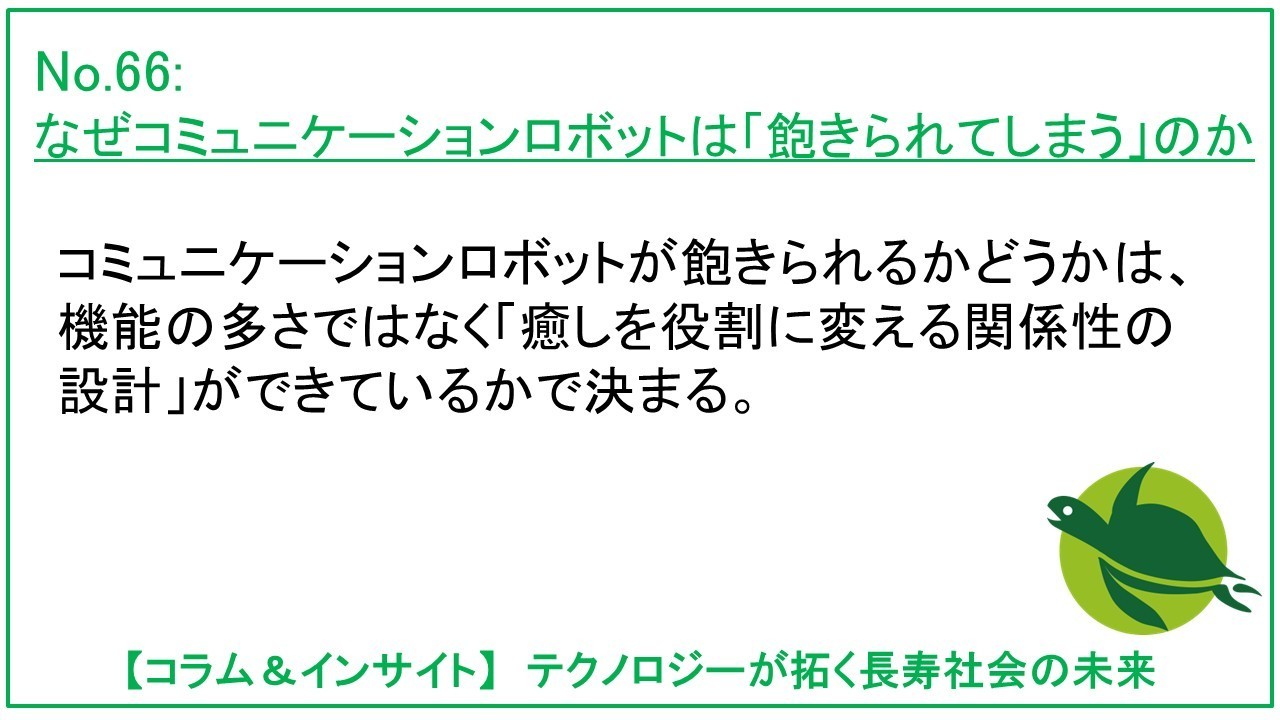シニア向けテクノロジー市場は、今後ますますの成長が期待されています。介護ロボット、AI見守りシステム、遠隔医療、バイタルデータのモニタリング技術など、新しい技術が次々と登場し、社会課題の解決に貢献しています。しかし、技術がどれほど優れていても、それだけでは市場に浸透しません。
特に小規模な開発企業がこの市場に新規参入する場合、単独では突破口を見出すのが難しく、「どのように市場に受け入れられるか」「どのように事業を継続・成長させるか」といった課題に直面しがちです。
そこで重要になるのが、「エコシステム」という考え方です。本コラムでは、エコシステムの基本概念、必要性、そして効果的な活用方法について解説します。BCG(ボストン・コンサルティング・グループ)が出版した書籍にも、事業領域間の壁は急速に崩壊しつつあり、次の10年の勝者の条件の一つとして、エコシステム化を制することが書かれていました。
ビジネスにおけるエコシステムとは、企業・パートナー・顧客・社会などが互いに影響し合いながら成長するビジネス環境 のことです。単独の企業では実現できない価値を生み出し、持続的な競争優位を確立できるのが特徴です。
例えば、アメリカのGAFAM(Google、Apple、旧Facebook、Amazon、Microsoft)のように、エコシステムをうまく編成・調整することで、圧倒的な企業価値を生み出すことに成功している企業もあります。
高齢・福祉のテクノロジー分野でも、企業単独ではなく、技術開発・サービス提供・導入支援・規制対応など、異なる分野のプレイヤーが連携することで、よりスムーズに市場を開拓し、事業を成長させることができるはずです。

エコシステムは、多くの企業が競争力を高め、持続的に成長するために取り入れている概念です。特に以下の3つの理由から、単独ではなく他の事業者と連携することが重要ではないでしょうか。
① 市場参入のハードルを下げる
新しい市場に参入する際、最大の壁となるのは「信頼の確立」です。どんなに優れた製品やサービスを提供していても、実績がなければ簡単には採用されません。しかし、すでに市場で信頼を得ている企業や団体と連携することで、新規参入企業もそのネットワークを活用し(巨人の肩に乗り)、よりスムーズに市場に受け入れられる可能性が高まります。
② 開発コストやリスクを分散できる
新技術の開発には、多くの資金と時間が必要です。すべてを自社でまかなうにはリスクが大きすぎるため、パートナー企業と協力し、開発資源を共有する、あるいは棲み分けを明確にすることで自社の負担を軽減できます。また、顧客ニーズの変化や市場動向に迅速に対応するためにも、他の事業者との連携は不可欠ではないでしょうか。
③ 持続可能なビジネスモデルを構築できる
短期的な売上だけでなく、長期的に安定した収益を確保できる仕組みを作ることが、企業の成長には不可欠です。エコシステムを活用することで、一度の取引で終わるのではなく、継続的にサービスを進化させ、市場の変化に柔軟に対応できます。例えば、単なるハードウェア販売にとどまらず、定期的なソフトウェアのアップデートやデータ解析サービスを提供することで、顧客の満足度を高めながら、ストック型の収益を確保できるモデルへと発展できます。
エコシステムの概念を理解する上で、多くの人が混同しやすいのが「協業」や「外注」との違いです。どちらも企業同士が連携する手法ですが、エコシステムにはそれらとは異なる特徴があります。
① 協業との違い
協業とは、特定の目的のために複数の企業が連携し、一緒に事業を展開することを指します。しかし、協業が基本的に「特定のプロジェクトや契約に基づいた一時的な関係」であるのに対し、エコシステムは長期的な成長を目的としており、関係者全体で価値を生み出しながら市場を拡大していく という違いがあります。
② 外注との違い
外注は、業務の一部を外部の企業や個人に委託することを指します。例えば、高齢者向けアプリを開発する際に、一部のプログラム開発を外注するケースなどが該当します。しかし、外注が「発注者と受注者の固定された関係」なのに対し、エコシステムでは各企業が独立しながらも相互に影響を与え合い、共に市場を育てていく関係を築く点が大きく異なります。
小さな企業でもエコシステムを効果的に活用するには、長期的な視点で価値を共創できる関係を築く必要があります。そのために、以下のステップを意識すると良いかと思います。
① 自社の強みと提供価値を明確にする
エコシステムに参加するには、まず自社の強みを明確にし、他の企業やパートナーとどのような相互関係を築けるのかを考えることが重要です。単なる「技術力」ではなく、市場のどの課題を解決できるのかを具体化し、他のプレイヤーとどのように補完し合えるのかを整理する ことが重要です。
② つながるべきパートナーを選定する
エコシステムの構築には、単なる取引先ではなく、ビジネス戦略を共に考えられるパートナーの選定が不可欠 です。例えば、
- 市場の参入や成長戦略を支援する専門家(営業支援、ネットワーク構築など)
- 技術開発の連携が可能な企業(自社アプリの追加機能としての連携先など)
- サービス提供をスムーズにする事業者(導入後のカスタマーサポートなど)
市場展開において、適切なパートナーとつながることが成功のカギになります。必要に応じて、専門家のサポートを受けながら、最適なエコシステムを構築していくことをおすすめします。
単独で市場を開拓するのは難しくても、適切なエコシステムを構築すれば、持続可能な成長が可能になります。市場戦略の立案からパートナー選定まで、一貫したアプローチをとることで、より強固な事業基盤を築いていきましょう。
セキグチについて

「いきいき長寿社会推進者セキグチ」の関口です。
テクノロジーを通じて、高齢者がより豊かに社会とつながる未来を目指し、介護ロボット分野から一歩広げた活動に取り組んでいます。私の経歴やこれまでの取り組みについては、プロフィールページで詳しく紹介しています。
また、活動の背景や大切にしている考え方は、ビジョン・メッセージページにまとめています。ぜひあわせてご覧ください。
最新コラム&インサイト
過去のコラムでもお伝えした通り、PAROやLOVOT、NICOBOといったコミュニケーションロボットは、「癒し」「話し相手」「孤独の解消」といった文脈で広く語られるようになりました。実際、それらは確かに重要な価値です。
しかし、現場で導入が進むにつれて、もう一つの大きな課題が浮かび上がってきています。それは、「最初は盛り上がるが、時間が経つと飽きられてしまう」という問題です。…
テクノロジーが拓く長寿社会の未来
テクノロジーと社会参加の両面から、長寿社会をより豊かにするための視点をわかりやすくお届けしています。
最新のお知らせ
2025年11月18日(火)
「介護ロボット経営実践会」に代わり、新ブランド「いきいき長寿社会推進者 セキグチ」として新サイトを公開しました。