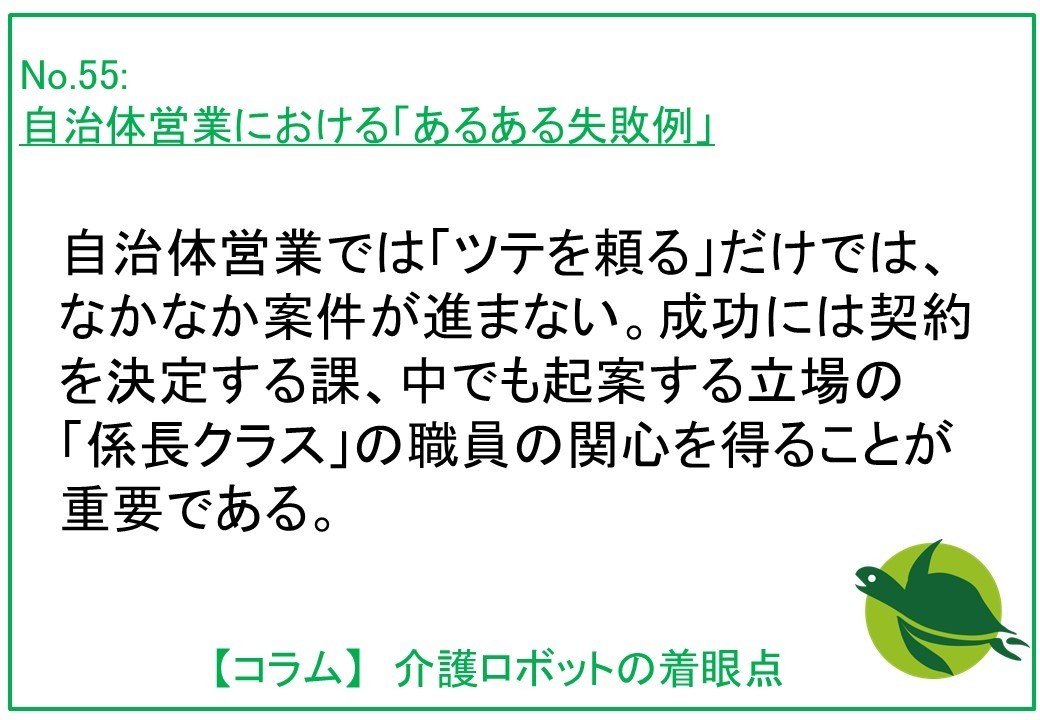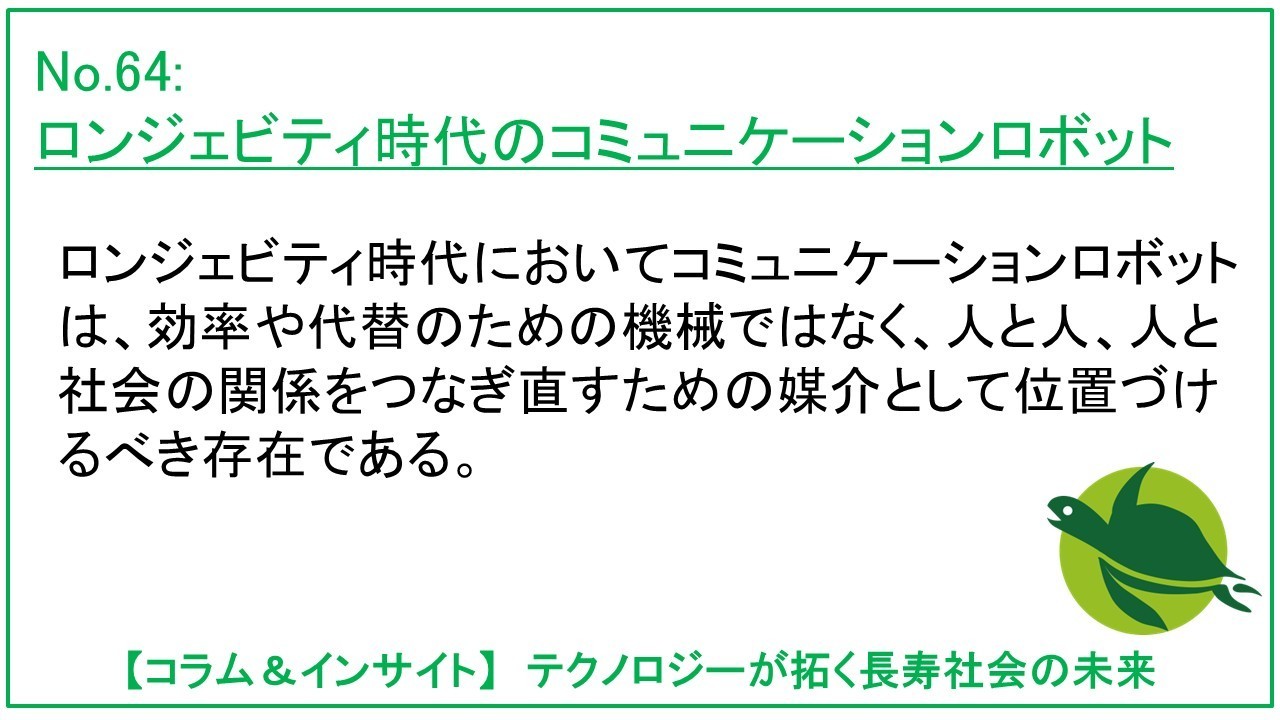今回のコラムでは、自治体営業で「ツテを頼る」ということを考えてみましょう。しかも、大企業や中堅企業ではなく、従業員数が50名にも満たない中小企業が「ツテを頼る」ということについて掘り下げてみます。
これまでに私がいろいろと目にしてきた自治体営業に関する解説書や記事を拝見する限り、書き手によって主張する内容が異なることに気がつきます。「ツテ」は本当に効果的なのか、それとも逆効果になり得るのか。これを具体的な事例を交えて検討していきます。
これまでに目にした自治体営業に関する主張として、2つの異なる立場を紹介します。
最初に紹介するのは、首長や副首長といった自治体のトップに直接アプローチすることを推奨する考え方です。東京にある小さなコンサルティング会社が自治体DXの仕事を獲得するために立ち上げたと思われる一般社団の公式サイトには、以下のような説明がありました。
「首長や副首長、企画部門の責任者など、自治体の意思決定に大きな影響力を持つ人物と良好な関係を築くことが求められます。キーパーソンの理解と支持を得ることで、庁内の調整がスムーズに進むようになります。」
さらに、キーパーソンへのアプローチにはトップセールスが効果的だと述べられています。経営者や役員クラスが直接自治体のキーパーソンに会って提案することで、事業の重要性と会社の本気度を伝えることができ、トップ同士の信頼関係が築かれれば、事業の推進力が格段に高まるというのです。
一方、もう一つの立場は、実務レベルの意思決定は各課が担っているため、トップへのアプローチは効果が薄いという考え方です。自治体営業を専門に行っている別のコンサル会社が出版した書籍には、次のように書かれていました。
「首長は選挙で選ばれた地域住民のリーダーですが、皆さんが自治体営業で折衝しなければならないビジネス上のトップではない、ということを意味しています。…いま、多くの首長が民間企業と連携して、地域を良くしようと奮闘されています。その場合でも、具体的な製品やサービスの導入検討、契約や発注などの実務は、例外的なケースを除き各課の管轄です。首長にアポイントをとってプレゼンするだけでは即契約には至らない理由が、おわかりいただけたかと思います。」
つまり、契約や導入の判断を担っているのは各課の職員であり、トップに働きかけても案件が動くわけではない、ということです。

実は、前者の「トップアプローチ」を推奨する考え方は、後者の会社が「自治体営業あるある失敗例」として繰り返し紹介している典型的なパターンです。
私自身の経験でも、トップセールスを行っても、その後担当課で却下されるケースを何度か見てきました。仮に首長や副首長に直接アプローチして話が盛り上がったとしても、最終的に導入を決めるのは担当課の課長や係長です。
トップセールスがうまくいったとしても、担当課の係長クラスが「今はそのタイミングではない」「導入する必要がない」と判断すれば、それ以上案件が進むことは難しいです。役所に連絡しても「またこちら(自治体側)から連絡させていただきます」などと伝えられるだけでしょう。
市長などの首長が庁内の課の1事業について、「●●の件は今、どうなっているんだ」などと必要以上に干渉すれば別ですが、そのような行為が行きすぎると、「この市長は業者から裏金を貰っているのでは?」「変な接待を受けたのでは?」などと疑われることになりかねません。
このように民間企業のトップに話をするのとは異なるのです。
「トップへのアプローチ」が必ずしも成功につながらないことがわかると、次に頼りたくなるのが「ツテ」です。例えば、地元の議員や関係者に紹介してもらい、役所の担当者に話をつけてもらうという方法があります。
一見すると効果がありそうに思えますが、これも実際には難しい場面が多くなります。例えば、誰かに議員を紹介してもらい、その議員さんから役所の要職に就いている人を紹介してもらうことを考えてみましょう。この場合、担当の課の職員と面談する機会を得ることは比較的容易になるでしょう。
しかし、その課の「担当者」が乗り気でなければ、案件が進むことはなく、結果的にうまくあしらわれてしまいます。しかも、いきなり「ノー」と伝えてしまうと紹介してくれた議員さんのメンツをつぶすことになるので、気を遣って1〜2回ほど面会してくれるはずです。担当者にとっては「ちゃんと会ってあげましたよ」という実績を残すことが目的になってしまい、案件そのものが進むわけではないのです。
では、どうすれば自治体営業を成功させることができるのでしょうか。従業員数が30名にも満たない中小企業が自治体に提案する場合、何十億円もの案件ではないでしょう。とにかく、最大のポイントは、課へのアプローチとなります。
特に重要なのは、起案する立場である『係長クラス』の職員に動いてもらうことです。契約や導入を決めるのは、結局のところ担当課です。首長や議員に話を通しても、担当課の係長クラスが「今は必要ない」と判断すれば、先述の通りで案件は前に進みません。
そのため、重要なのは「導入の見込み度」や「課内での関心度」を効率よく見極めることです。その見極めの結果によって、対応が変わってくるはずです。
見込み度が低い自治体については、タイミングを見計らう必要があります。焦って地元の議員を通じてプッシュしても、労力の割に成果が限定的になるのです。
最後にまとめますが、「ツテを頼る」ことは一見効果的に思えますが、実務レベルで案件を前に進めるためには、担当課の職員、特に「係長クラス」の賛同が不可欠です。そこで、まず「導入の見込み度」や「課内での関心度」を見極めることが重要です。
トップセールスやツテによるアプローチに頼るのではなく、実際に意思決定権を持つ現場の担当者に「必要だ」と思わせることこそが、案件を進めるカギになるのです。
セキグチについて

「いきいき長寿社会推進者セキグチ」の関口です。
テクノロジーを通じて、高齢者がより豊かに社会とつながる未来を目指し、介護ロボット分野から一歩広げた活動に取り組んでいます。私の経歴やこれまでの取り組みについては、プロフィールページで詳しく紹介しています。
また、活動の背景や大切にしている考え方は、ビジョン・メッセージページにまとめています。ぜひあわせてご覧ください。
最新コラム&インサイト
これまでのコラムでも紹介してきた「ロンジェビティ」という言葉があります。
ロンジェビティという言葉が示すのは、単に寿命が延びる社会ではありません。
それは、人生の後半が長くなることを前提に、…
テクノロジーが拓く長寿社会の未来
テクノロジーと社会参加の両面から、長寿社会をより豊かにするための視点をわかりやすくお届けしています。
最新のお知らせ
2025年11月18日(火)
「介護ロボット経営実践会」に代わり、新ブランド「いきいき長寿社会推進者 セキグチ」として新サイトを公開しました。