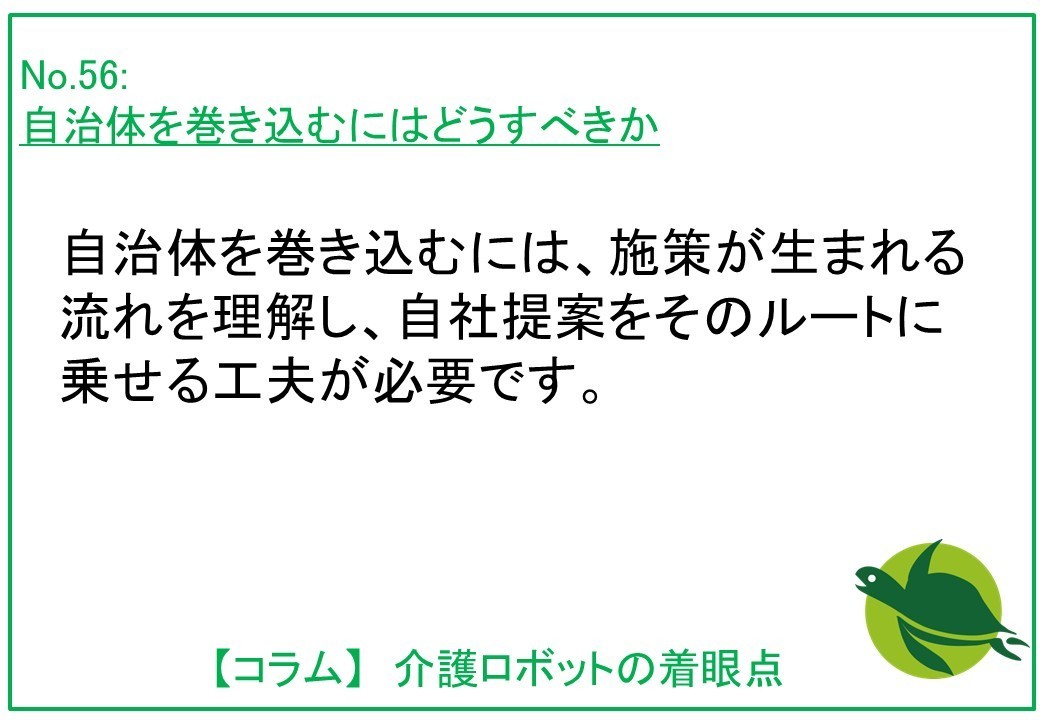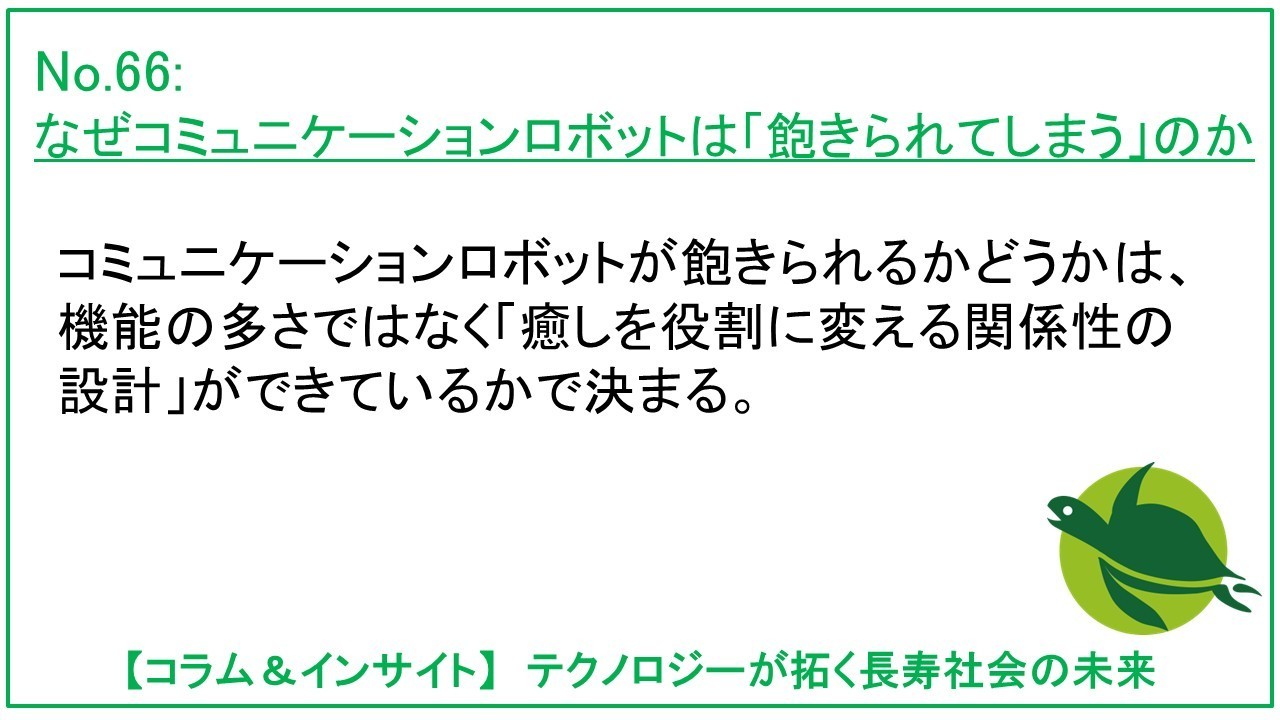中小企業の中には、「自治体を絡めて事業を拡大したい」「市場を開拓するには、自治体を巻き込むのが良いのでは?」と考える経営者も少なくありません。
特に、高齢者支援や地域活性、防災・防犯、介護・福祉分野の製品やサービスを展開する企業にとって、自治体との連携は有力な選択肢の一つです。
ただし、「役所に提案すればうまくいく」と考えて動くのは見通しが甘すぎます。そもそも、自社のアイデアが自治体の施策として成立しうるのか、どのような流れで制度化・事業化が実現するのか、ある程度の調査と構想が不可欠です。
つまり、「この市場はいけそうだ」「条件次第で可能性がある」「難しそうなので見送ろう」といった経営判断を下すためには、仮説構築と事前調査が必要です。そして「いけそうだ」と判断したら、次に誰にどうアプローチすべきかを検討する段階に進みます。
ここで参考になるのが、島根県浜田市長・久保田章市氏の著書『役所のしくみ』です。私はこの本をタイトルを見て即購入しました。著者が現職の市長という点に加え、私自身が過去に浜田市の企業を支援した経験があり、何度か現地を訪れたことがあったからです。
久保田市長は著書の中で、自治体内で施策が発案される主なルートとして、以下の5つを紹介しています。
1. 国が提供する好事例情報
各省庁のウェブサイトなどで紹介されている「好事例集」を参考にして、自治体が他市町の成功事例を模倣するケースです。行政内では、事例が国のウェブサイトに掲載されているということが一定の「お墨付き」として機能し、採用されやすくなる傾向があります。
2. 地方議員からの提案
提案で多いのは、議員が地盤とする地域の困りごとや要望です。例えば、「道路の草刈り助成額を引き上げてほしい」「〇地区の市道が狭いので拡幅してほしい」など、身近な困りごとが行政に持ち込まれることが多いといいます。
3. 市民からの提案や要望
これは、市に直接要望や提案する方法です。浜田市では「市長直行便」という制度があり、市民が専用のはがきやメールで市長に直接要望や提案を伝えることができます。“直訴”型のルートです。

4. 職員の発案(ボトムアップ)
久保田市長によれば、職員からの自発的な施策提案が増えることは、市役所の活性化につながるとのこと。ただし、実際には課長や部長による“ストップ”もあり、制度化には多くのハードルがあるといいます。
このことは言い換えれば、情報(提案)を当該課の職員に届けるだけでは不十分であり、課長クラスにも確実に伝え、理解・納得してもらう必要があるということです。
5. 首長の発案(トップダウン)
地域訪問時の声や、新聞・雑誌・テレビなどから得た情報がヒントとなり、首長が施策を発案するケースです。首長の意志や関心が直接政策につながるという点で、影響力の大きいルートです。
では、介護ロボットや福祉機器、アプリ、ICTソリューションを企画・開発・販売する中小・ベンチャー企業が注目すべき発案ルートは、どれなのでしょうか?
5つのルートすべてがヒントになりますが、特に以下の3点は実務に直結する示唆を含んでいるかと思います。
その1)国の好事例として紹介されることの影響力
たとえその評価が賛否ある内容であっても、国のホームページで「好事例」として紹介された施策は、多くの自治体がこれを模倣しやすい傾向があります。
つまり、製品やサービスを採用した自治体での成功事例を「国の好事例」として掲載してもらうことができれば、それ自体が新たな拡販の導線になるのです。
その2)自社製品の“視察効果”とメディア掲載の力
市長の例では、現場視察で得た情報が新たな施策に結びついていますが、同様のことは部課長クラスの職員にも起こります。視察先で貴社製品が使われていれば、それが次なる施策の“きっかけ”になる可能性があります。
また、その様子が地元メディアや業界メディアに掲載されれば、議員や首長の目に触れ、さらに波及効果が広がるでしょう。
現に私は実務を通じてこれを痛感しました。何もしていないのに「視察させてもらえないか」「取材を受けてくれないか」という話が毎日のように舞い込んできたのです。
単に導入してもらうだけでなく、「見られる」「伝えられる」ことが、次なる展開を生む重要な要素なのです。
その3)協力者による波及
しかし、「国に好事例として認められる」「メディアに取り上げられる」ためには、先に導入してくれる「協力者」の存在が不可欠です。現場で実際に使われていなければ、国の視察もメディアの取材も生まれません。
つまり、最初の実績を作らなければ、何も始まらないのです。実績がないと、どこからも相手にされず、にっちもさっちもいかなくなります。
これこそが、小さな企業が自治体市場を開拓しようとする際に立ちはだかる、大きなハードルです。
一般市場であれば、知人や仲間に顧客役を頼み、「これが実績です」と演出することもできますが、自治体相手にはそんな姑息な手段は通用しません。

自治体市場に参入するためには、「どのように提案するか」だけでなく、「自治体の中でどうやって話が動くのか」を知ることが重要です。
今回紹介した5つの施策発案ルートを踏まえれば、単なる売り込みではなく、「仕組みの中にどう入っていくか」という視点が見えてくるはずです。
また、残念ながら「良い製品だから、売れる」ということはありません。初めから前述の内容や構造を理解し、理想のシナリオを描くと同時に、どこにどのようなハードルがあるかを把握しておくことです。
セキグチについて

「いきいき長寿社会推進者セキグチ」の関口です。
テクノロジーを通じて、高齢者がより豊かに社会とつながる未来を目指し、介護ロボット分野から一歩広げた活動に取り組んでいます。私の経歴やこれまでの取り組みについては、プロフィールページで詳しく紹介しています。
また、活動の背景や大切にしている考え方は、ビジョン・メッセージページにまとめています。ぜひあわせてご覧ください。
最新コラム&インサイト
過去のコラムでもお伝えした通り、PAROやLOVOT、NICOBOといったコミュニケーションロボットは、「癒し」「話し相手」「孤独の解消」といった文脈で広く語られるようになりました。実際、それらは確かに重要な価値です。
しかし、現場で導入が進むにつれて、もう一つの大きな課題が浮かび上がってきています。それは、「最初は盛り上がるが、時間が経つと飽きられてしまう」という問題です。…
テクノロジーが拓く長寿社会の未来
テクノロジーと社会参加の両面から、長寿社会をより豊かにするための視点をわかりやすくお届けしています。
最新のお知らせ
2025年11月18日(火)
「介護ロボット経営実践会」に代わり、新ブランド「いきいき長寿社会推進者 セキグチ」として新サイトを公開しました。