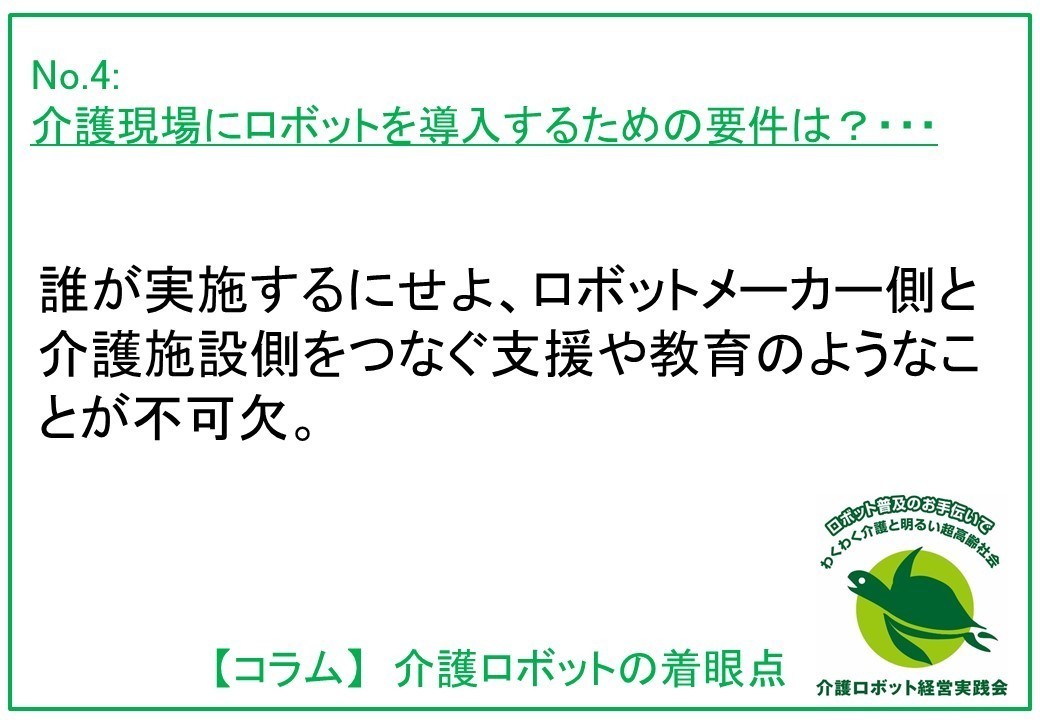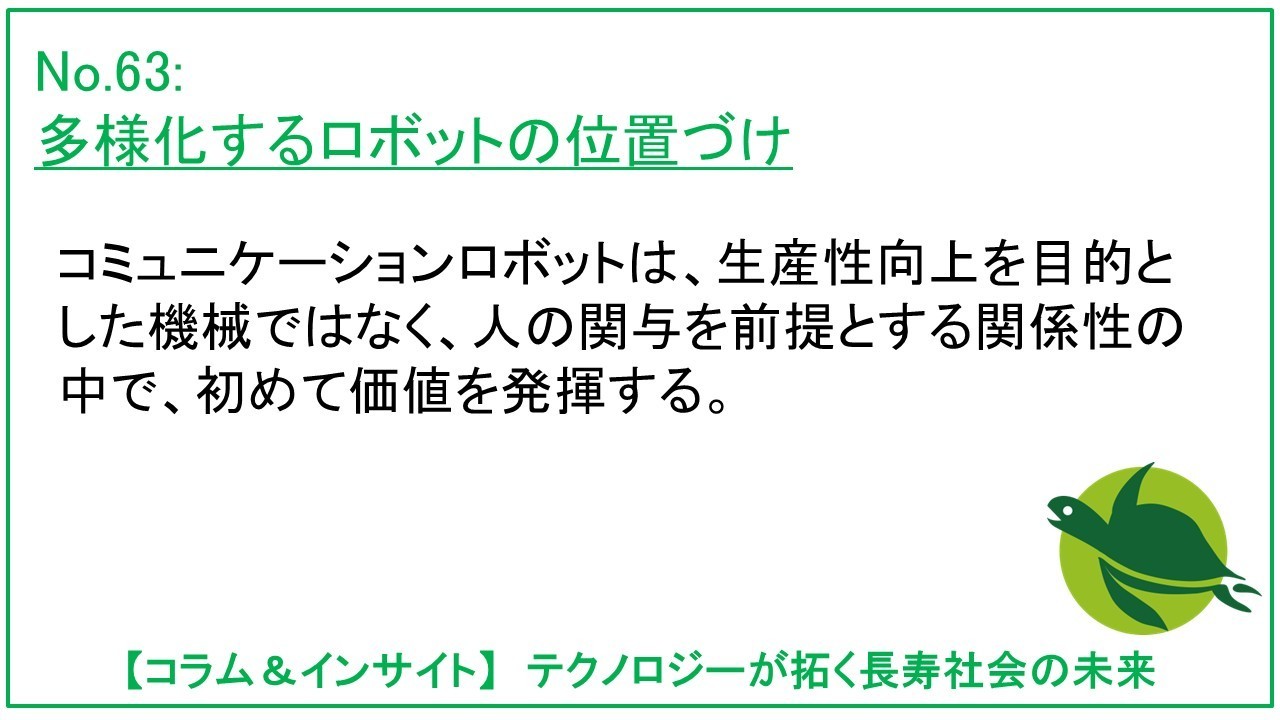2016年 6月 20日(月)
【キーワード】
- 支援
- 教育
- 意識改革
去る6月14日(火)に開催された埼玉県事業の「埼玉県 リハビリ・介護ロボット研究会」のパネルディスカションでモデレーターを務めさせていただきました。テーマは「介護施設へのロボット導入の課題とそのソリューションについて」(→ こちらの記事も参考に!)。
今回のコラム「介護ロボットの着眼的では」、そのパネルディスカションの中で指摘された素晴らしい意見をいつくかご紹介します。
Q: 介護ロボットを施設に上手く導入して活かすために、(メーカー側に要求するばかりではなく)施設としてはどのような努力を行うべきか?
パネルディスカションには介護施設から3名の方が参加されましたが、その中の1人が施設にリフトを導入された際の取り組みを紹介してくれました。その取り組みでは、リフトという機械を導入するに際し、法人内で勉強会を開催して、職員の意識改革に時間を割いたとのことです。
同時に、利用者さんやその家族からリスト導入に関する理解を得るための努力をされたそうです。また、その方は介護ロボットを施設に上手く導入して活かすために要件として現場のアセスメントと職員に対する教育の必要性を主張していました。
また、別の施設の方は、ビジョンの共有化と主張されました。これはどこの法人でも職員同士の考え方や意見がバラバラになりがちですが、皆が同じ方向に向かって進んでいかれるようにまずはビジョンの共有が必要であるという意見です。
パネルディスカションでは、施設だけではなくロボットメーカーからも3名がパネリストとして参加されました。
Q:介護という市場は他にロボットが導入されている市場と比べて、どういう特徴があるか?
パネリストの一人曰く「工場などで使われる産業用ロボットは、決まった工程を決まった設定の中で動くことになるが、介護では人がロボットを使い、コスト面を含めて想定外のことが多い」と。
今回のパネルディスカションでハッキリしたことは、介護現場にロボットを導入する場合、産業用ロボットのように決まった工程で、しかも決まった設定の環境下で使うケースとは大きく異なるということ。
それを認識した上で、ロボットメーカーには施設に対する対応(支援)が求められるということです。一方で、介護施設の方も、職員の意識改革、ビジョンの共有などに取り組む必要があるとのことです。
いずれにせよ、誰が実施するにせよ、ロボットメーカー側と介護施設側をつなぐ支援や教育のようなことが不可欠である。これが今回のパネルディスカションでは共通の認識でした。
セキグチについて

「いきいき長寿社会推進者セキグチ」の関口です。
テクノロジーを通じて、高齢者がより豊かに社会とつながる未来を目指し、介護ロボット分野から一歩広げた活動に取り組んでいます。私の経歴やこれまでの取り組みについては、プロフィールページで詳しく紹介しています。
また、活動の背景や大切にしている考え方は、ビジョン・メッセージページにまとめています。ぜひあわせてご覧ください。
最新コラム&インサイト
前回のコラムでは、「テクノロジーと共に生きる時代へ」というテーマで、技術が私たちの暮らしに深く溶け込み始めている現実についてお伝えしました。
今回はその流れを受けて、コミュニケーションロボットについて考えてみたいと思います。…
テクノロジーが拓く長寿社会の未来
テクノロジーと社会参加の両面から、長寿社会をより豊かにするための視点をわかりやすくお届けしています。
最新のお知らせ
2025年11月18日(火)
「介護ロボット経営実践会」に代わり、新ブランド「いきいき長寿社会推進者 セキグチ」として新サイトを公開しました。