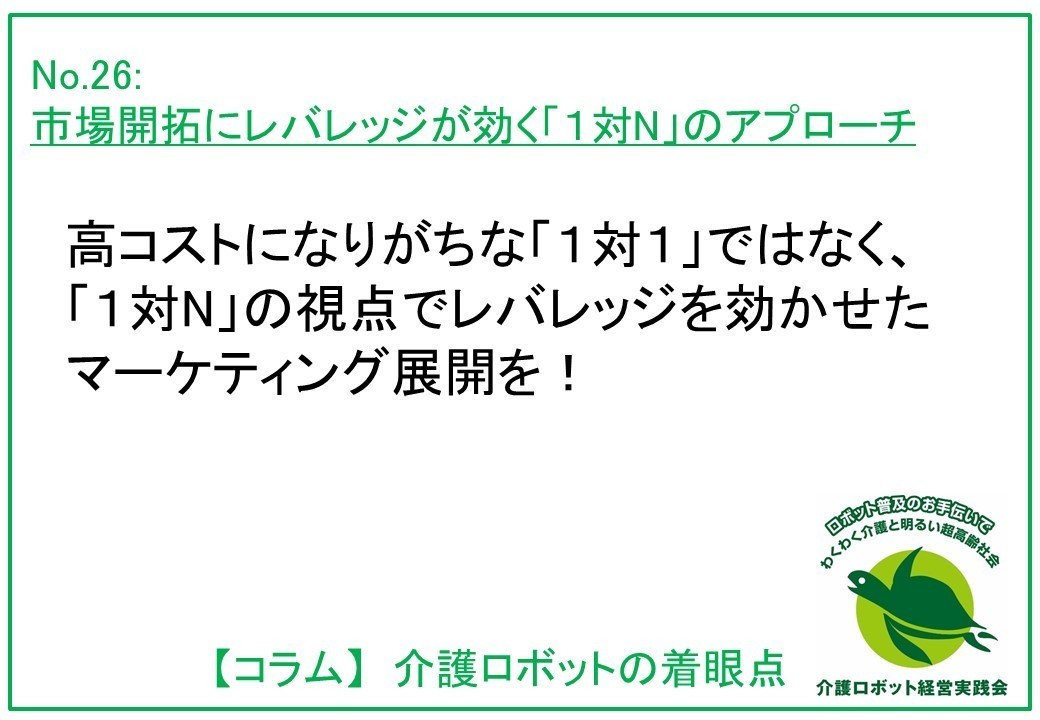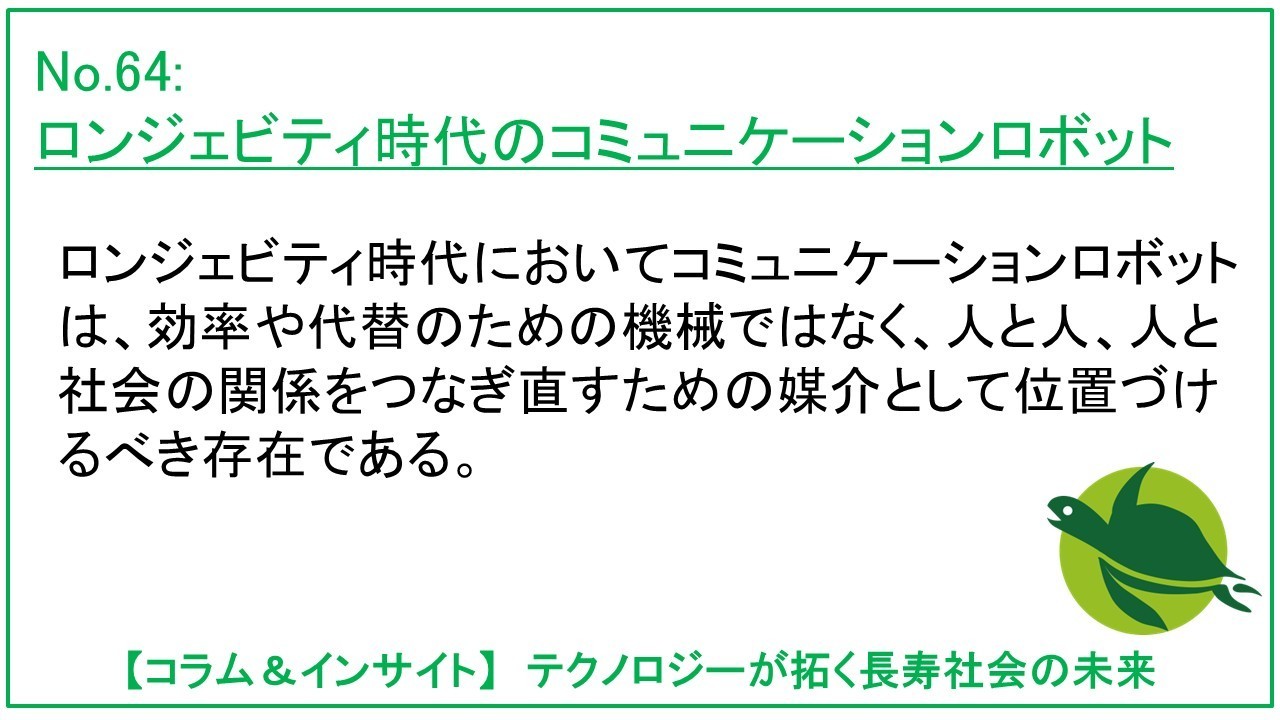2017年 12月 28日(木)
【キーワード】
- 1対Nの視点
- 顧客にも動いてもらう
- セミナー
介護ロボットの販売という商売を考えた時、ロボットというモノの存在を潜在顧客である施設の人に知ってもらい、興味を持ってもらい、購入という行動に移してもらって初めて「お金」が入ってきます。
仮に2度、3度と自社営業マンが施設にデモや説明に出向いたところ、「購入」してもらえなければ、営業マンの人件費や交通費などの費用がかさむばかり。1円たりとも費用の回収ができません。
しかも、施設から「ロボット(モノ)売りの業者」として見られている限り、彼らはメーカーや代理店側に営業や販売コストが掛かっていることなど気にもしないでしょう。
「業者」として見られている限り、施設から購入するつもりなどハナからなくても興味本位で「デモに来てくれ!」と言われ、遠方まで出向くこともあるでしょう。
出向いたところ、「わざわざデモに来てくれたのだから、何か買わないとマズイかな?」などと気に掛けてくれることは、残念ながら期待できません。
また、苦労の末に購入してもらっても、翌日から問題なく活用してくれるケースは少なく、一定以上のフォローが必要なロボット機種が多いかと思います。
そこで、デモの延長のごとく、2度、3度、4度と個別に訪問してフォローすることになります。これはロボットを導入した施設にとって非常にありがたい話ですが、自社の別機種の販売や広報活動につながらない限り、メーカーや代理店にとってはコスト増を招くばかりです。
でも、それが現実ではないでしょうか?
介護ロボットの販売という商売では、一般的にどこの業界でも言われている新規顧客の獲得コストだけではなく、購入後のコストについてもよく検討しなければなりません。なぜなら、売ったらオシマイというモノ売りでは済まされないからです。
ただ、このような新規顧客の獲得や購入後のフォローについては、「1対1」で対応している限りコスト高になりがちです。
販売価格から仕入れ値を差し引いた「粗利」でご飯を食べるビジネスモデルの場合、いかに顧客獲得コストを低く抑えるかが重要となります。同時に、購入後に発生するコストを低く抑えなければなりません。
つまり、低コストで新規顧客を獲得し、その後のフォローも可能な限りコストを抑える一方で拡販につなげたいもの。
そこで、考えられる方法があります。自社の営業マンだけが頑張る、あるいは代理店の数を増やすのではなく、顧客にも動いてもらうことです。顧客に協力者になってもらうことです。
購入してくれた施設の人が「これは良いよ!」と介護業界の仲間に伝えてくれることは、非常にありがたいことです。
購入してくれたお客さんが
「ウチの施設でもはじめは上手く使えなかったよ。でもこういう取り組みをしたら、使えるようになった!」
「しかも、今では○○という目標を掲げ、達成率は80%のところまできている!」
「今では職員のやる気が以前とはまるで違う!」
などとプラスのメッセージを業界に発信してくれるとありがたいですね。
「ありがたい」というより、業者扱いされる営業マンが売りの匂いを出しながらデモや説明に出向く直接営業よりも、このような同じ目線の業界仲間の言動の方が遥かに信用に値するし、説得力があります。
ただ、これを行なうにしても「1対1」の方法では広がりが限定され、コスト高を招くことになります。
そこで有効な方法なのが「1対N」という視点です。これが今回の本題です。
「1対N」の視点で考えられる方法にはインターネットの駆使が挙げられます。
わざわざ1件1件訪問しなくても、動画を見てもらえば済むケースも多いはず。例えば、基本的な操作方法や代表的な活用シーンの紹介などがそれに該当します。
ところが、「市場の特性」を踏まえなければなりません。介護は日頃からインターネットを積極的に駆使して仕事をする業界ではありません。
インターネットで新規顧客を獲得して、フォローもインターネットで…というわけにはいかない業界です。そこで「1対N」の視点を上手く活かす方法として相応しいのが、複数の顧客(含:潜在顧客、既存客)が集まる「場」を用意することです。
このような場の例として、自治体などが開催する介護ロボットセミナーがあります。自治体のイベントに便乗すればメーカーや代理店は集客コストゼロで自社製品のお披露目が可能です。
私はこれまで何十回と自らイベントを企画・開催しました。講演者としてお呼ばれされた回数も数十回を超えています。
ただ、多くのセミナーでは、「ロボットの展示者」としてメーカーや代理店が関わるにすぎません。あるいは、それにプラスして多少の製品説明の時間が与えられる程度です。
営業マンが来場者に直接説明するスタイルで、来場した施設の人は実物(ロボット)を見て、触ることができます。
この方法なら確かに「1対N」の場になります。しかし、決して特定企業向けのイベントではないので、「顧客にも動いてもらう」や「顧客に協力者になってもらう」というわけにはいきません。
でも、自治体主催にも関わらず、実はそれに近いイベントを企画したこともありました。そこでは、私がコーデイネーターを務め、導入している施設の職員から活用方法のポイントなどをディスカッションしながら引き出すという方法でした。
これはまさに「顧客にも動いてもらう」あるいは「顧客にも協力者になってもらう」方法であり、単なる「ロボットの展示」に比べるとメーカーさんの満足度は相当高かったようです。
とにかく、「1対N」の視点を上手く活かすことです。レバレッジを効かすのです。何でも「1対1」では高コストになりがちですから。そのためには、複数の顧客(含:潜在顧客、既存客)が集まる「場」を用意して・つくってあげること。
それを上手に仕組み化し、自治体のイベントに便乗するだけではなく、自社のマーケティング活動にそれを組み込むことが相応しいはずです。
詳しいことは、こちらの教材の中で説明しています。
セキグチについて

「いきいき長寿社会推進者セキグチ」の関口です。
テクノロジーを通じて、高齢者がより豊かに社会とつながる未来を目指し、介護ロボット分野から一歩広げた活動に取り組んでいます。私の経歴やこれまでの取り組みについては、プロフィールページで詳しく紹介しています。
また、活動の背景や大切にしている考え方は、ビジョン・メッセージページにまとめています。ぜひあわせてご覧ください。
最新コラム&インサイト
これまでのコラムでも紹介してきた「ロンジェビティ」という言葉があります。
ロンジェビティという言葉が示すのは、単に寿命が延びる社会ではありません。
それは、人生の後半が長くなることを前提に、…
テクノロジーが拓く長寿社会の未来
テクノロジーと社会参加の両面から、長寿社会をより豊かにするための視点をわかりやすくお届けしています。
最新のお知らせ
2025年11月18日(火)
「介護ロボット経営実践会」に代わり、新ブランド「いきいき長寿社会推進者 セキグチ」として新サイトを公開しました。