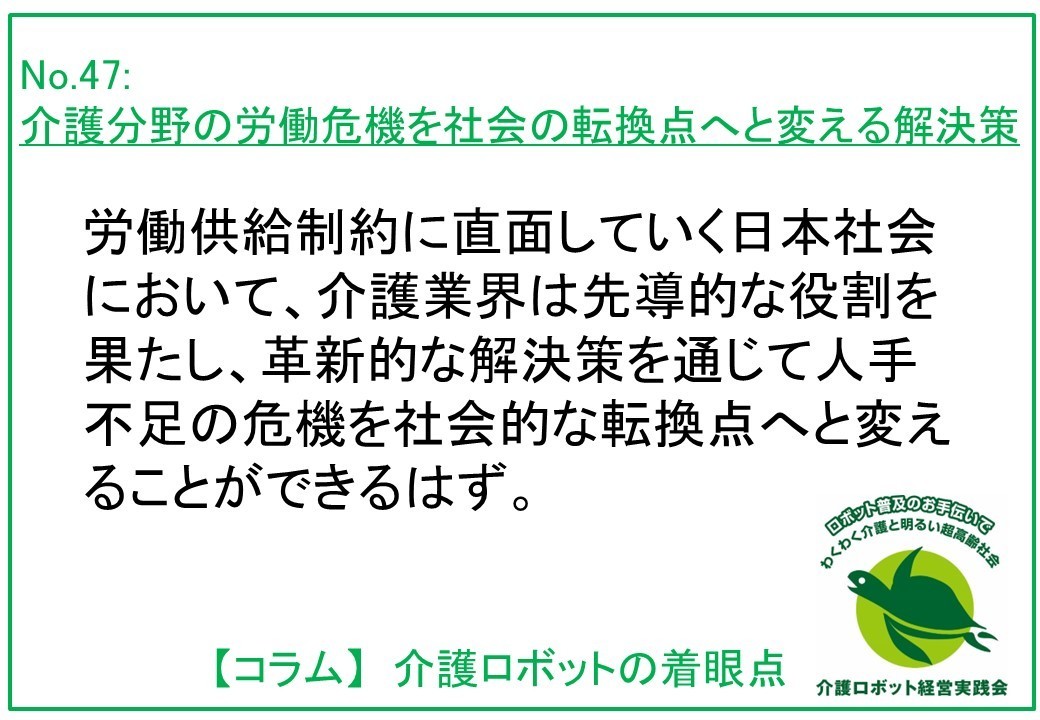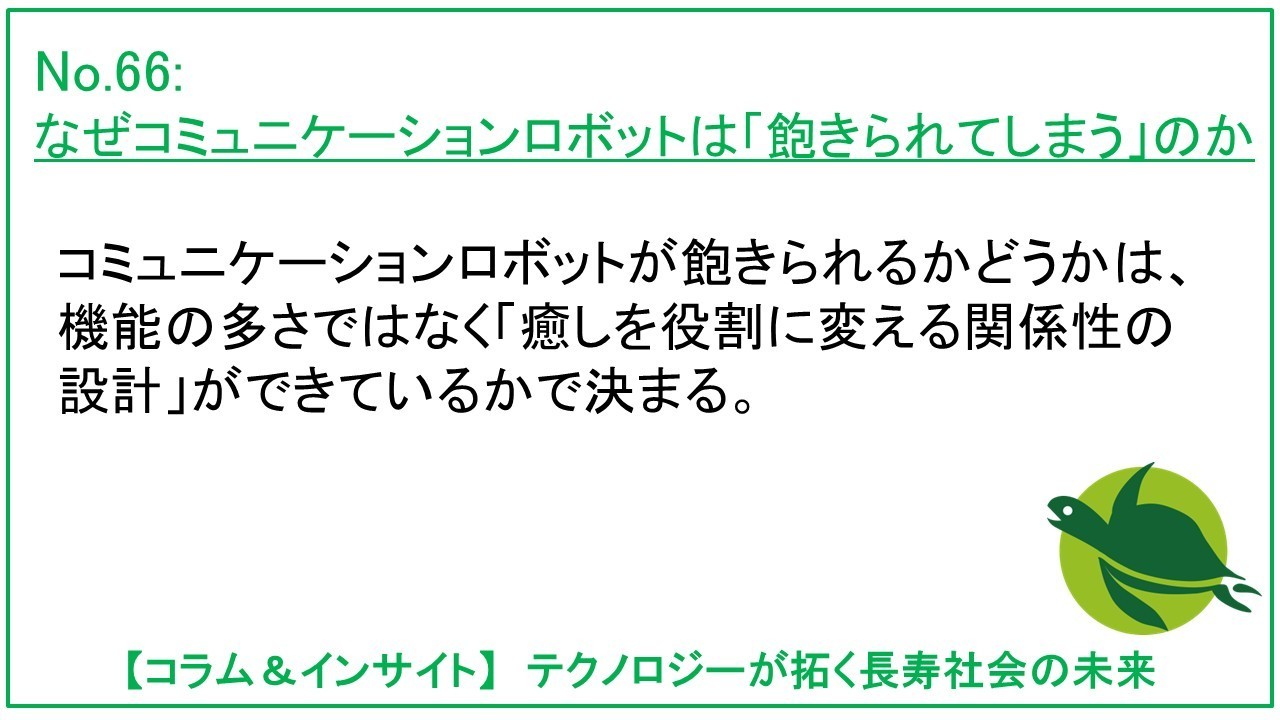プレジデント社から先月出版された『「働き手不足 1100万人」の衝撃』という本を読む機会がありました。この書籍を通じて、現代の日本社会が直面する前例のない構造的な人手不足の問題について再認識することができました。人口動態統計が示す通り、この問題は今後さらに深刻化する一方です。
このコラムでは、書籍の内容を踏まえつつ、特に介護分野を例に日本社会が直面する問題と解決策について考えてみます。
書籍では、人手不足の問題が、従来の景況感や企業業績の変動とは異なり、労働供給の根本的な不足によって引き起こされていることが強調されています。これまでの人手不足は需要と供給の変動によるものでした。しかし、今後は供給側の限界、すなわち労働力そのものの不足が原因になるとのことです。書籍には、「労働供給量がボトルネックになって発生する労働供給制約社会になる」と書かれていました。
介護分野においても、労働供給制約社会の問題はさらに深刻化します。それに、仮に働き方改革などを行って介護職の働き手不足が解決されとしても、結果として別の領域で新たな人手不足が生じてしまいます。なぜなら、労働供給制約社会では、「余っている分野から足りない分野に人を動かす」という人を右から左に動かすことで解決することはないからです。
人手不足は介護分野に限りません。政府が外国人労働者の在留資格「特定技能」の受け入れ枠を2024年度からの5年間で現行の2倍以上の82万人を受け入れることを自民党に提示したというニュースが数週間前に報道されましたが、これは問題の重大さを物語っていると考えています。
NHKが2023年半ばより「働いてクライシス」と題して放送した特集は、全国で発生している深刻な人手不足問題に注目を集めたようです。これは経済的な側面だけでなく、日本の社会構造そのものに深く関わる問題として捉えられています。今でも多くの経営者が「どうしたらいいのか分からない」と感じており、解決策を見つけるための試行錯誤が続いているようです。しかし、本書にはこの労働供給制約という危機が、日本社会を根本から変えるチャンスとなる可能性があることも示唆されています。この危機を突破口として、より豊かで持続可能な社会への変革を目指すことが可能なのかもしれません。
そんな労働供給制約社会になっていく中、解決策として書籍には4つの提言が紹介されていました。それらは「機械化・自動化」「ワーキッシュアクト」「シニアの小さな活動」「仕事におけるムダ改革」となります。
これを介護分野に当てはめて考えてみましょう。1つ目の「機械化・自動化」は、まさに介護ロボットやICTなどの積極的な活用ということになります。私が2010年から関わってきた活動そのものです。今のところ当初の思惑通りに市場は成長しませんでしたが、(2010年頃と比べると)非効率で時間を要する手書きがかなり少なくなり、これまで多くの時間を割いていた記録業務については大きく効率化が進んだと考えています。
2つ目の「ワーキッシュアウト」というのは、娯楽や趣味・コミュニティ参加のような本業の労働・仕事以外で、「誰かの困りごとや助けてほしいという需要に応えている」活動を指します。ワーキッシュアクトを介護分野に応用することは、地域コミュニティの中で高齢者支援の新たな形を生み出し、介護サービスの提供を広げることが可能になります。
3つ目の「シニアの小さな活動」については、自治体が行う「介護支援ボランティアポイント制度」の積極的な展開が大きな役割を果たすと考えています。この制度を活かすことで、高齢者自身が介護分野の小さな活動に従事し、活躍する機会を増やすことができます。
最後に、「仕事におけるムダ改革」についても触れたいと思います。ここでも「介護支援ボランティアポイント制度」が果たす役割は非常に大きいです。
たとえ施設の職員が、過剰な負担(ムリ)、不均等(ムラ)、無駄(ムダ)を排除するノウハウを持っていなくても、大手製造業等で業務改善に取り組んできたシニアの豊富な経験を生かせるはずです。
そのためには、介護支援ボランティアポイント制度が対象とする業務を、「草むしり」や「掃除」といった単純な雑用からより専門的で知的な内容へと拡大することが必要です。


このようなアプローチを積極的に取り入れることで、介護分野だけでなく、日本社会全体の人手不足問題に対する長期的な解決策を見出すことができるはずです。これらの取り組みは、働く人々の環境を改善し、サービスの質を向上させることで、介護分野だけでなく、日本社会全体にポジティブな影響を与えるでしょう。
セキグチについて

「いきいき長寿社会推進者セキグチ」の関口です。
テクノロジーを通じて、高齢者がより豊かに社会とつながる未来を目指し、介護ロボット分野から一歩広げた活動に取り組んでいます。私の経歴やこれまでの取り組みについては、プロフィールページで詳しく紹介しています。
また、活動の背景や大切にしている考え方は、ビジョン・メッセージページにまとめています。ぜひあわせてご覧ください。
最新コラム&インサイト
過去のコラムでもお伝えした通り、PAROやLOVOT、NICOBOといったコミュニケーションロボットは、「癒し」「話し相手」「孤独の解消」といった文脈で広く語られるようになりました。実際、それらは確かに重要な価値です。
しかし、現場で導入が進むにつれて、もう一つの大きな課題が浮かび上がってきています。それは、「最初は盛り上がるが、時間が経つと飽きられてしまう」という問題です。…
テクノロジーが拓く長寿社会の未来
テクノロジーと社会参加の両面から、長寿社会をより豊かにするための視点をわかりやすくお届けしています。
最新のお知らせ
2025年11月18日(火)
「介護ロボット経営実践会」に代わり、新ブランド「いきいき長寿社会推進者 セキグチ」として新サイトを公開しました。