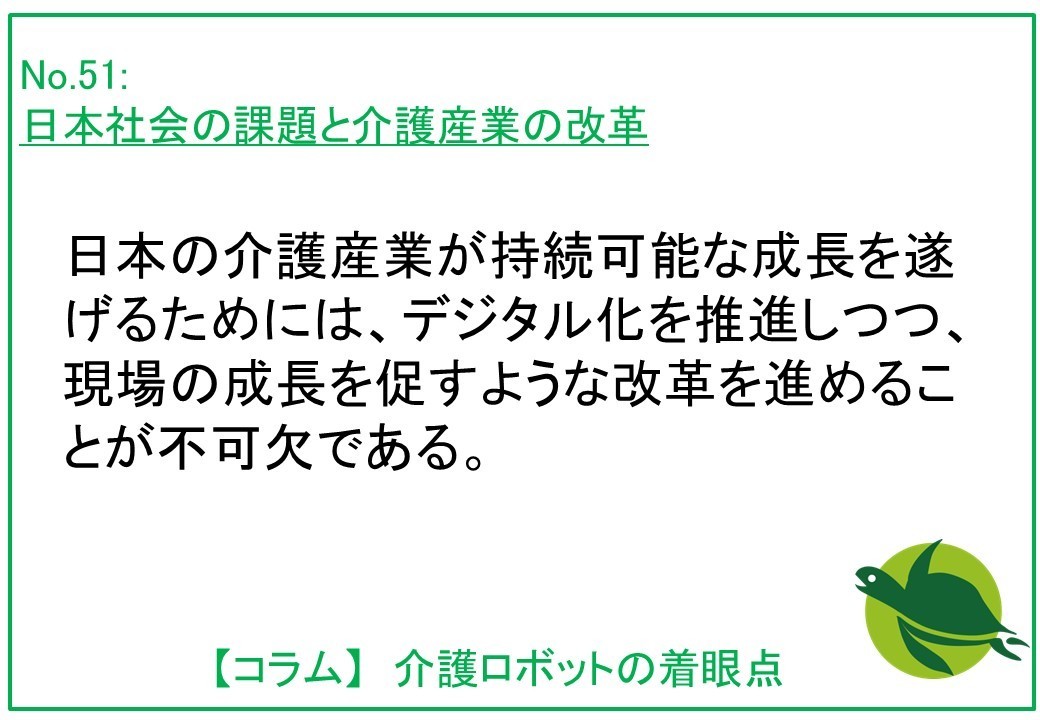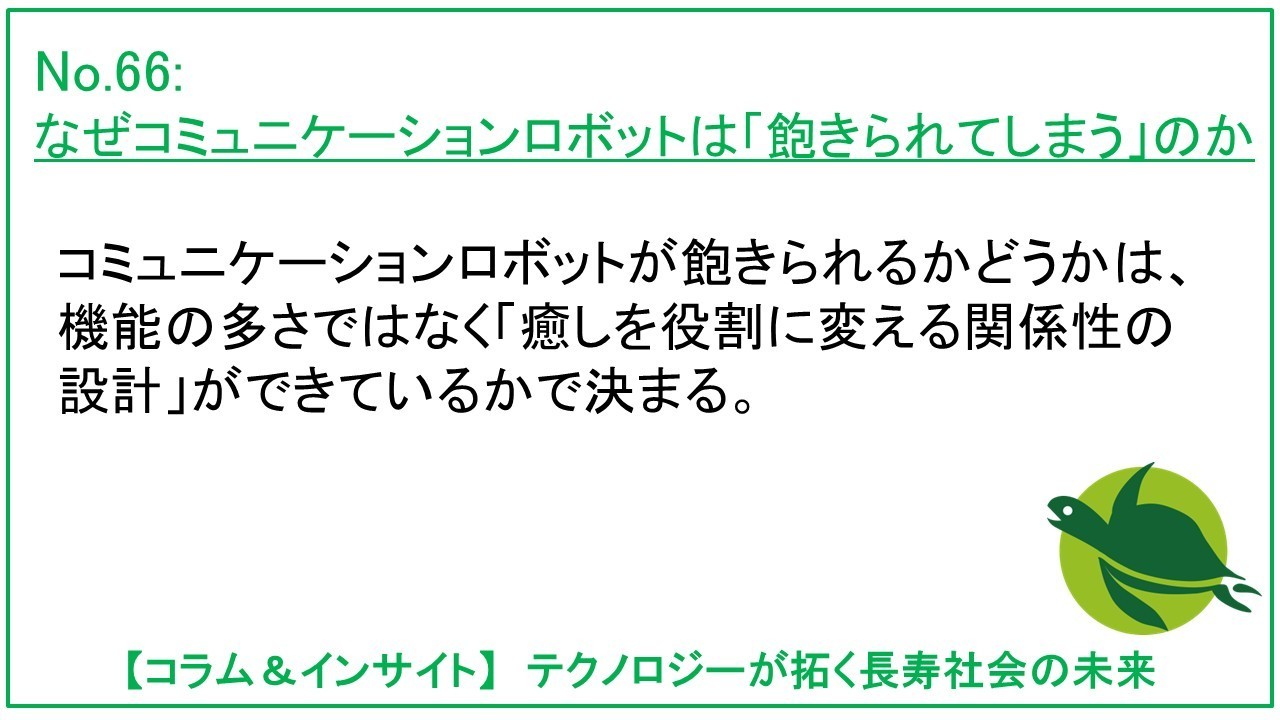お盆休みの間に、以前読んだ野口悠紀雄氏の「プア・ジャパン」という本を再読しました。日本は少子高齢化が進み、社会全体が抱える課題も複雑化しています。その中でも特に注目されるのが、医療・介護分野です。これらの分野は今後、就業者数で日本最大の産業となることが予想されていますが、その成長を支えるには解決すべき問題が山積しています。
野口氏が「プア・ジャパン」で述べているように、日本社会の抱える構造的な問題は、補助金を与えるような表面的な改革では解決できません。このコラムでは、医療・介護分野の将来像を見据え、必要な改革について考察したいと思います。
日本社会が直面している最も大きな変化の一つが、医療・介護分野の急成長です。高齢化が進む中で、これらの産業は急速に拡大しており、10年も経たないうちに就業者数では日本一の産業となると予想されています。しかし、この拡大が必ずしもポジティブなものとは限りません。
野口氏が指摘するように、生産性の低い介護のような産業で就業者数が増加し、生産性の高い製造業の労働力が減少することで、社会全体の生産性が低下し、経済成長を阻害する可能性があります。
別の本では、「医療・介護業界が今後も生産性上昇をともなわずに高齢人口の増加・高齢者の高齢化により膨張してしまう場合には、何が起きるか。そうなれば、日本経済は減少する貴重な労働力を医療・介護業界に無尽蔵に使わざるをえない状況になる」と警告しています。
「プア・ジャパン」というタイトルが示す通り、野口氏は日本が「賃金の低い国」になってしまったことを嘆いています。この現象は、EPAや技能実習制度などを通じて多くの外国人労働者を受け入れてきた介護業界にも大きな影響を及ぼしています。賃金が低くなれば、日本へ稼ぎに来る外国人労働者の数が減少し、逆に日本の労働者が海外に流出するリスクが高まります。
野口氏は、日本経済が遅れてしまった最大の原因として、デジタル化の遅れを挙げています。「本来であれば不要な仕事に、多大な労働力が費やされている。これがデジタル化されれば、仕事の効率性は大きく向上するだろう」と述べています。
しかし、医療・介護分野ではデジタル技術の導入が遅れ、効率性の向上が阻まれています。デジタル化が進めば、事務作業の効率化やデータ管理の精度向上など、さまざまな面で生産性が向上し、介護の質も向上することが期待されます。
介護現場ではロボットやICTツールの導入が進んでいますが、まだ十分とは言えません。その理由の一つは、単にツールを導入するだけでは効果を発揮しないからです。2010年から多くのロボット導入現場を見てきた私は、テクノロジーの効果的な運用にはスキル(教育)や体制の整備(組織)が不可欠であると、翌年の2011年頃から痛感していました。
野口氏が本の中で述べているように、「補助によって改革と創造の力が削がれ、甘えと依存の構造が広がる。それは、古い社会制度をますます強固なものにしてしまうだろう」というリスクがあります。
補助金は、日本の産業構造を固定化し、改革の意欲を削ぐ危険性を持っています。介護ロボットやICTの普及推進に関する国や自治体の政策についても、「補助金依存体質になった日本の製造業」と同じ轍を踏んでいるのではないかと思われます。
だからこそ、介護分野においては、補助金を与えるだけでなく、介護施設側が自主的な改革とイノベーションを推進するための仕組みが必要です。国や自治体は、補助金制度を作り、それを配ることが目的となってしまいがちですが、それではあまりにも不十分です。
もっと長期的な視点から、介護現場での効率性や介護の質を向上させるための取り組みが求められます。介護施設を監督する立場にある役所が、前例踏襲主義になりがちな仕事のやり方を大きく変え、自らデジタル化を積極的に推進する存在にならないと、なかなか話が進まないかもしれません。
就業者数で日本最大の産業となる医療・介護分野における人材育成は、今後の日本社会において最も重要な課題の一つです。現状では給与水準が低く、優秀な人材を正規職員として採用することが困難です。この問題は、人材紹介会社に高い手数料を払えば解決するような簡単なものではありません。しかも、今が一番人材を獲得しやすい時期であり、3年後、5年後にはさらに困難になることが予想されます。
だからこそ、野口氏が指摘する通り、デジタル化によって生産性を大きく高める必要がありますが、補助金を活用してツールを購入し、既存の職員だけで何とかしようとするのは限界があります。ロボットやICTは、現状から理想的な姿へ到達するためのツールにすぎません。これらを最大限に活用するためには、もっと戦略的なアプローチが求められるのです。
正規職員の採用が難しい中で、他に選択肢がないわけではありません。例えば、外部人材を戦略的に活用する方法があります。介護現場では、自分たちが不得手とする分野を補完する形で、経済的な負担にならない範囲内で外部人材を活用すれば、生産性を向上させるとともに、サービスの質を向上させることができるはずです。
野口氏が「プア・ジャパン」で指摘するように、日本社会が再び豊かさを取り戻すためには、根本的な社会構造の改革が必要かと思います。特に、医療・介護分野でのデジタル化と生産性向上は、今後の日本の経済成長に不可欠です。デジタル化の推進と共に、現場の成長を促すような改革を進めることで、医療・介護分野の発展が日本全体の経済成長を牽引する力となるでしょう。
セキグチについて

「いきいき長寿社会推進者セキグチ」の関口です。
テクノロジーを通じて、高齢者がより豊かに社会とつながる未来を目指し、介護ロボット分野から一歩広げた活動に取り組んでいます。私の経歴やこれまでの取り組みについては、プロフィールページで詳しく紹介しています。
また、活動の背景や大切にしている考え方は、ビジョン・メッセージページにまとめています。ぜひあわせてご覧ください。
最新コラム&インサイト
過去のコラムでもお伝えした通り、PAROやLOVOT、NICOBOといったコミュニケーションロボットは、「癒し」「話し相手」「孤独の解消」といった文脈で広く語られるようになりました。実際、それらは確かに重要な価値です。
しかし、現場で導入が進むにつれて、もう一つの大きな課題が浮かび上がってきています。それは、「最初は盛り上がるが、時間が経つと飽きられてしまう」という問題です。…
テクノロジーが拓く長寿社会の未来
テクノロジーと社会参加の両面から、長寿社会をより豊かにするための視点をわかりやすくお届けしています。
最新のお知らせ
2025年11月18日(火)
「介護ロボット経営実践会」に代わり、新ブランド「いきいき長寿社会推進者 セキグチ」として新サイトを公開しました。