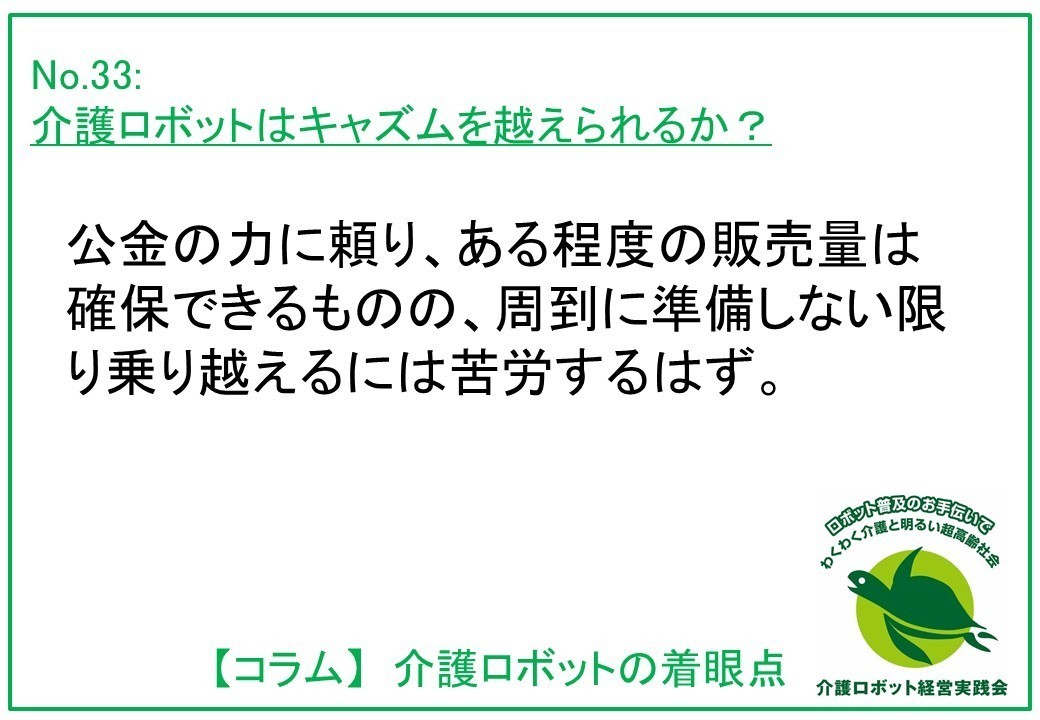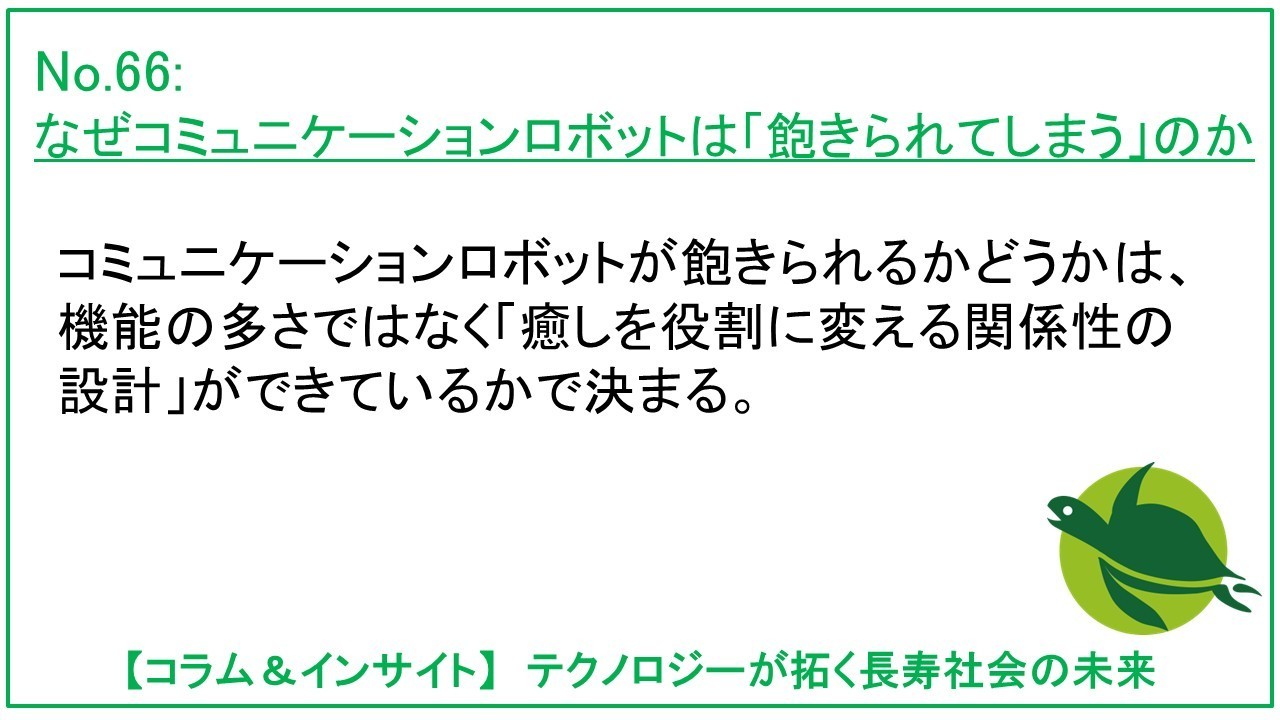2018年 9月 26日(水)
【キーワード】
- 市場開拓
- キャズム
いきなり難しい話からのスタートとなりますが、「キャズム理論」というのを聞いたことがあるでしょうか?
今回は、介護ロボット市場の形成、特に「キャズムを越えられるか?」という視点で話を進めていきます。
キャズム(chasm)とは、「深い裂け目」「岩盤や氷山にできた巨大な亀裂」のことです。少数の進歩派によって構成される初期市場と、一般的な利用者からなる主流市場との間には、大きな裂け目があると言われますが、それがキャズムです。アメリカのムーア氏によって提唱されました。
ところで、キャズムを説明するに際し、「イノベーター理論」というアメリカ・スタンフォード大学のエベレット・ロジャース教授が提唱したイノベーション普及に関する理論を知っておくと良いので少し説明します。
これは商品購入に対する態度を購入の早い順に5つに分類したものです。その5つは、Innovators(革新者)、Early Adopters(初期採用者)、Early Majority(前期多数採用者)、Late Majority(後期多数採用者)、Laggards(採用遅滞者)となります。
つまり、このように順を追ってモノが普及していくということです。
最初に購入するInnovators(革新者)は冒険好きな人たちです。彼らは、新しい知識を手に入れたがります。新しいモノが市場に出ると飛びついて購入する人たちです。
介護ロボットについても、他のモノが市場で普及する時と同じように、そのようなInnovators(革新者)と呼ばれる人たちが最初に購入しました。
そして、Innovators(革新者)の次にEarly Adopters(初期採用者)と呼ばれる人たちが購入することになります。
そして…と続けたいのですが、ここまでは順調だったにも関わらず、次のEarly Majority(前期多数採用者)と呼ばれる人たちに採用されることなく(市場に普及せずに)、残念ながら市場撤退ということがよく起こります。それがキャズムの典型パターンです。
私は3-4年前から「介護ロボットは、キャズムを越えられるか?」ということがかなり気になっていました。
これまでの市場形成を見る限り、「売り手」も「買い手」も公金に頼った格好でした。そんな中、果たしてキャズムを超えられる製品はどれだけあるでしょうか?
今の公金に頼った市場開拓では越えられない製品が少なくないと思っています。代理店は、上手くいかないからと、2つ目、3つ目、…と取扱い製品を増やしてチャンスを追い求めるものの、勝ちパターンを見い出すことができないまま時間が過ぎていき…。
幸いなことに「モノづくり」に公金が投入され続けているので、新製品が今後も次から次と開発されていきます。それらが後に市販化されるはずです。そして公金の力に頼りある程度の販売量は確保できます。
しかし、それ以降はあらかじめ周到に準備しない限りかなり苦労することになるはずです。成り行きのシナリオだとキャズムを越えることができないということです。
そこでキャズムについて書かれた本を読んでみましたが、そこには面白いことが書かれていました。Innovators(革新者)やEarly Adopters(初期採用者)の人たちは、イノベーションの可能性を追求するので、少々使い勝手が悪くても、不便な点は創意工夫して利用するとのこと。
一方、Early Majority(前期多数採用者)の人たちは、イノベーションを変革のための手段とは考えることはなく、生産性の向上やコスト削減など実利的な結果を重視するとのこと。
要するに顧客の購買心理が異なるということ。市場の特性が異なるのです。
そこで私が読んだ本の解説によると、キャズムを越えてEarly Majority(前期多数採用者)の人たちに受け入れてもらうためには命題が3つあるとのことです。それらは次の通りです。
- 具体的かつ実利的な目に見える成果
- 工夫なしに簡単に使えるユーザー・インターフェイス
- 過去の実績
介護ロボット向けに言い換えると、導入初期の苦労など無く簡単に使えて、職員の負担軽減などの成果が明らかに実感できる製品となります。
また、上記3つの命題を満足させる方策については、次の4つが読んだ本の中に示されていました。
- ニッチ市場の選定
- ホールプロダクトの構築
- ポジショニングの設定
- 流通チャネルと価格の設定
1つ目は「ニッチ市場の選定」ということですが、介護ロボットの「見守り」「移乗介助」などの分野はすでにニッチ市場となります。
そこで介護ロボットの場合は「ニッチ市場」というよりも、特定のユーザーと言い換えた方が良いと考えています。それは自社製品の魅力を最大限に引き出して活用してくれるユーザー(施設)です。
そういうユーザー(施設)に受け入れられることが、後の波及効果につながります。これがキャズムを超える第一歩です。これについては、私が前々から「協力施設の育成」と主張していたことと同じです。
2つ目に出てきた「ホールプロダクトの構築」とは、完全パッケージの製品やサービスのことです。ホールプロダクトで重要なのは、解決策をトータルに提供するということ。これは私が前々から主張していた「導入・活用の支援」が該当するのではと考えています。
ユーザーである施設にモノを提供するだけでは不十分であり、完全パッケージにはならないのです。詳しくは、こちらのページに少し解説があります。
3つ目の「ポジショニングの設定」に移りますが、特に製品数が多い「見守り」にはそれが重要だと常々感じていました。これは、自社製品が競合と比較して、相対的にどのような位置にあるのかを示してあげることです。
見守り機器のように似たような製品が多数ある場合、ユーザー(介護職員)から見ると何が何だか違いがよくわからないはずです。私にもよくわかりません。
だから機能面について「ああだ!こうだ!」と詳細な説明をする前に、自社製品が見守り機器の中で相対的にどのような位置にあるのをユーザー(介護職員)に示してあげた上で、自社製品について理解してもらう必要があると考えていました。
4つ目の「流通チャネルと価格の設定」に関しては、読んだ本によると注目すべき販売チャネルは直販とのこと。この方式は、顧客と直に商談し、顧客の問題点を浮かび上がらせ、その解決方法を提案できるから優れているとのこと。ハイテク製品など、機能が複雑なものは、需要を作り出す上で最適の販売チャネルとのことですが、当たり前の内容ですね。
最後になりますが、ムーア氏は上記の方策を推進しながら、ニッチ市場でリーダーシップを獲得するとともに、口コミ効果を活用しつつ、周辺ニッチ市場を攻略する!
そのようなシナリオを描くことを提唱していますが、それはまさに戦略の公式なのです。
セキグチについて

「いきいき長寿社会推進者セキグチ」の関口です。
テクノロジーを通じて、高齢者がより豊かに社会とつながる未来を目指し、介護ロボット分野から一歩広げた活動に取り組んでいます。私の経歴やこれまでの取り組みについては、プロフィールページで詳しく紹介しています。
また、活動の背景や大切にしている考え方は、ビジョン・メッセージページにまとめています。ぜひあわせてご覧ください。
最新コラム&インサイト
過去のコラムでもお伝えした通り、PAROやLOVOT、NICOBOといったコミュニケーションロボットは、「癒し」「話し相手」「孤独の解消」といった文脈で広く語られるようになりました。実際、それらは確かに重要な価値です。
しかし、現場で導入が進むにつれて、もう一つの大きな課題が浮かび上がってきています。それは、「最初は盛り上がるが、時間が経つと飽きられてしまう」という問題です。…
テクノロジーが拓く長寿社会の未来
テクノロジーと社会参加の両面から、長寿社会をより豊かにするための視点をわかりやすくお届けしています。
最新のお知らせ
2025年11月18日(火)
「介護ロボット経営実践会」に代わり、新ブランド「いきいき長寿社会推進者 セキグチ」として新サイトを公開しました。