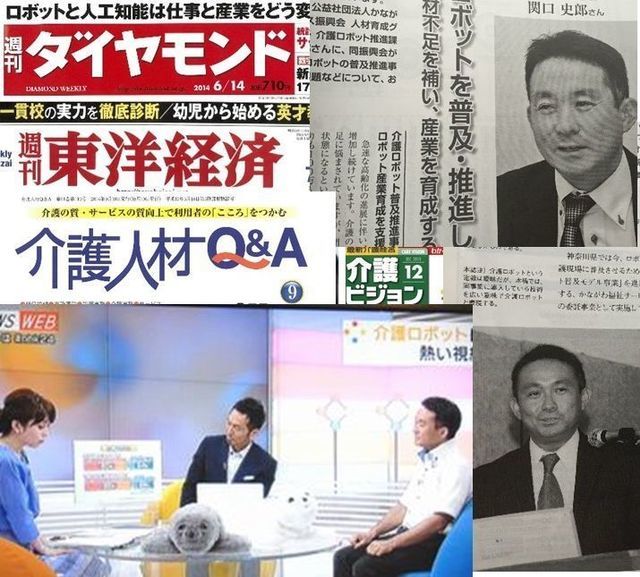介護ロボット経営実践会では、「マーケティング戦略強化で市場開拓のスピード化」という支援コンセプトを掲げ、新規に介護市場へ参入する、あるいは参入して間もない企業(大企業~中小企業)の新規事業に対して支援を行っています。適宜、必要なアドバイスを提供しながら、よりスピーディーに市場で成長することができるようサポートします。

当会は、新規参入や参入間もない事業に対して、特異な介護市場での効果的な参入および拡販を支援するアドバイザーとしての役割を担います。
この市場において欠かせない顧客育成、自治体との連携、適切なビジネスモデルの構築など、必要な知識とスキルを伝授し、成功のための基盤作りをサポートします。
貴社のリソースおよび立ち上げステージに合わせた最適な解決策を提示し、早期に成長軌道に乗り、ひとり立ちできるよう導きます。

具体的な支援内容は以下の通りです
新規参入支援
- 介護市場に新しく参入する企業や、参入して間もない企業に対して、新規立ち上げのサポートを提供します。
アドバイザリーサービス
- 新規事業に対して、特異な介護市場での効果的な参入および拡販を支援するためのアドバイスを行います。
- 市場開拓に欠かせない顧客育成、自治体との連携、適切なビジネスモデルの構築を通じて、企業が早期に成長軌道に乗るようサポートします。
その他
- 経営戦略やマーケティング戦略の策定を支援します。
- 新規開拓のために行う見込み客(介護施設)向けのセミナーやワークショップの講師を務めます。
- その他、ご相談ください。
【特別レポート】
介護ロボット・ICT市場開拓の秘訣:なぜ上手くいかないのか? 成功するための戦略とマーケティング
このレポートでは、市場で成功するための戦略とマーケティングの要点を詳しく解説しています。なぜ上手くいかないのか、どのように顧客と市場を理解し、競合との差別化を図るのかを明らかにします。さらに、見える化や導入支援などの具体的なアプローチも紹介。これを読めば、介護市場での成功のカギが見えてきます。
現場で役立つ実践的なガイドラインを手に入れ、他社に一歩先んじましょう!登録不要。今すぐにご確認いただけます。
当会の支援サービスを初めてご利用いただく方には、「単発相談」をお勧めしています。このサービスは販売事業者向けに提供されており、オンラインで行われます。無料でご利用いただけます。
単発相談

無料の単発相談サービスをZoomで提供しています。このサービスは、以下のような販売事業者に特におすすめです。
- 自社のマーケティング戦略についてアドバイスを受けたい
- セミナーの開催や顧客との効果的なコミュニケーション方法について知りたい
- 新たなビジネスモデルの導入や既存モデルの改善を検討している
無料の単発相談サービスを通じて、具体的なアドバイスや実践的なヒントを得ることができます。貴社の成功をサポートするための第一歩として、ぜひご活用ください。お申し込みをお待ちしています。
販売事業者向けセミナー

当会では、介護市場で販売を拡大したい企業向けに、最大2.5時間の出張型セミナー(オンラインも可能)を開催しています。このセミナーは、「前半:セッション」と「後半:相談」の2つのパートから成り立っています。
セミナーの対象は主に2つのグループに分かれます。一つは、新たに参入する、あるいは参入したばかりの企業です。もう一つは、すでに複数の機種で代理店契約を結び、販売活動を行っている企業です。
前半のセッションでは、約80~90分をかけて、介護施設向けのマーケティング戦略を当会独自の視点から詳しく解説します。販売が終了した教材「ロボット市場開拓のマーケティング」に記載された内容についても一部説明します。
後半の相談では、参加者と共に貴社が直面している課題や次のステップについてディスカッションを行います。このセミナーを通じて、新しい視点や戦略を共有し、具体的な成功への手順を共に考えていくことを目指しています。
さらに、当会の詳しい支援内容についても情報提供いたします。料金は9万円(+税)となります。
介護市場の特性に基づき、販売事業者である貴社には戦略やマーケティングの支援を提供します。一方、潜在的な顧客である施設に対しては、売り込みではなく、オペレーションの改善や経営力向上に焦点を当てたサポートを提供します。これにより、貴社と買い手とのギャップを埋め、販売につなげるお手伝いをします。
気軽にお知らせください

販売事業者向け支援の内容について、何かご不明な点がございましたら、どうぞお気軽にお知らせください。
「お問い合わせフォーム」をご利用いただけます。
会社紹介
介護ロボット
お役立ち情報
【No.50】公務員の常識を覆すDX戦略の現場から
【No.49】地方創生マネーの実態と課題
【No.48】地方自治体のデジタル変革:市民サービスの改善への道
【No.47】介護分野の労働危機を社会の転換点へと変える解決策
【No.46】介護予防事業の問題点と克服への道筋
【No.45】補助金が、自主性や積極的な改革の意識をダメにする?
【No.44】介護ロボの普及:国や自治体の補助金政策は何が問題なのか?
【No.43】コロナ禍で介護ロボットの普及は阻まれるのか?
【No.42】分厚いレポートと保険給付外の市場の可能性
【No.41】販売事業者は、どのようにセミナーを開催するべきか?
【No.40】製造業のサービス化が進んでいく中、介護ロボットは?
【No.39】縦割りの弊害とカニバリゼーション
【No.38】介護ロボットのセミナーやアンケートの活かし方
【No.37】介護ロボットの普及は「見える化」が解決してくれる
【No.36】介護ロボットの普及・市場開拓のブレイクスルー
【No.35】介護ロボットの買い手の効用を妨げているものは?
【No.34】平成31年度の補助金は早期争奪戦か?
【No.33】介護ロボットはキャズムを越えられるか?
【No.32】産業用と異なるからこそ必要なこと
【No.31】介護ロボット販売で先にやるべきこと
【No.30】成功への第一歩はメニューに載ること?
【No.29】 過去のターニングポイントと面白い取り組み
【No.28】 平成30年度の介護ロボット予算で気付いたことは…
【No.27】ロボット活用に向けた施策で最も重要なことは…
【No.26】市場開拓にレバレッジが効く「1対N」のアプローチ
【No.25】介護ロボット市場の開拓にも必要なユーザー教育
【No,24】誰が介護ロボット市場を制するか?
【No.23】介護ロボット代理店の苦労
【No.22】ロボットビジネスのセグメント化
【No.21】「ニーズの違い(バラツキ)」とイベント企画
【No.20】施設が補助金に飛びつく前にやるべきこと
【No.19】施設にとってロボットの導入で最も重要なことは?
【No.18】ロボットをロボットとして見ているだけでは?
【No.17】ロボット市場への参入は凶と出るか吉と出るか?
【No.16】ロボットセミナーの開催で判明した顧客のニーズ
【No.15】潜在顧客から見た見守りロボット
【No.14】介護ロボットは6年前より増えたが、その一方【No.13】見守りロボットは是か非か?
【No.12】介護ロボットを活用する直接的なメリット
【No.11】ロボットに頼らない活用方法は?
【No.10】施設の介護ロボット選定の実態は?
【No.9】介護ロボット市場の開拓には?
【No.8】補助金政策による光と影
【No.7】補助金のメリットとデメリットは?
【No.6】自治体支援策の特徴は?
【No.5】ハードだけではなく、ソフト面も必要では?
【No.4】介護現場にロボットを導入するための要件は?
【No.3】なぜ、「普及はまだまだ!」なの
【No.2】介護ロボットの認知度は飛躍的に高まったが
【No.1】介護ロボットの普及を電子カルテと比べると